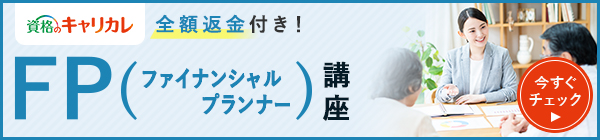FP2級試験は参考書を活用して勉強しよう!どんな選び方がいい?

FP2級資格に合格すると、就職に有利になることや、キャリアアップ・年収アップなどのメリットがあります。FP2級試験への合格には、参考書を活用しての勉強が効果的が、参考書の数は多岐にわたるため、どのような選び方をすると良いのか前もって知っておきたいところです。ここでは、参考書・テキスト選びについて詳しく解説しますので、是非の参考にしていただければと思います。
目次
FP2級に合格するには、どのような参考書が必要なの?
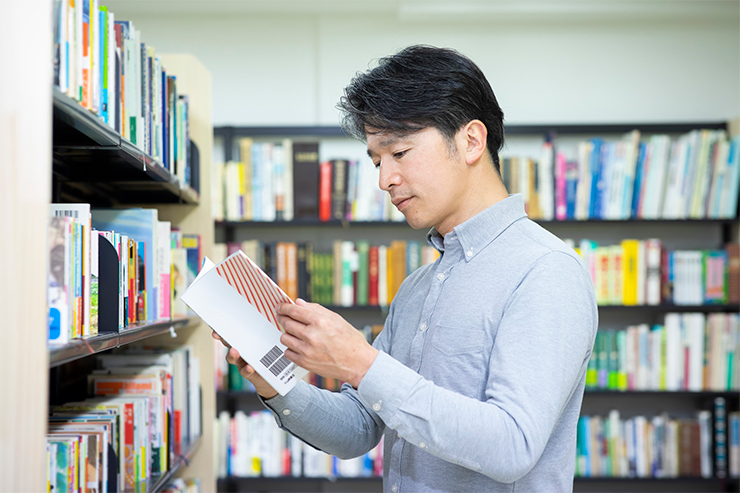
FP2級合格に向けての参考書・テキスト選びは、試験申込の時点で方向性が決まると言っても過言ではありません。
その理由についてご説明します。
受検する実技試験によって選ぶ
FP2級の試験は、FP3級と同様、日本FP協会ときんざい(一般社団法人金融財政事情研究会)の2機関が実施します。
学科試験は、両機関とも共通の内容ですが、実技試験は機関ごとで内容が異なります。
実技試験は、両機関とも記述式での筆記試験ですが、FP協会は「資産設計提案業務」についての問題を、90分以内で40問解答します。
これに対し、きんざいでは「個人資産相談業務」「中小事業主資産相談業務」「生保顧客資産相談業務」「損保顧客資産相談業務」の4つから、受検申請の際に選択する形式となっており、同じく90分以内で5問解答します。
どの業務を選ぶかは、受検申請時に選択しないといけません。
試験対策として選ぶ参考書も、選択した実技試験に合わせて選ばないといけないのは、このような理由があるためです。
受検しない実技試験の参考書・テキストを買ってしまうと、適切な試験勉強ができなくなってしまいます。
参考書によって、対応度合いはさまざまであり、目次を見ても分かりにくいものも多いようです。
選ぶときには十分注意しましょう。
選択する実技試験によっては、参考書がほとんど見られない
FP2級試験は、年3回実施されます。
きんざいの実技試験は、先ほどご紹介したように4つから選択しますが、そのうち中小事業主資産相談業務は年2回(9月・1月)の実施です。
また、損保顧客資産相談業務は年1回(9月)のみの実施です。
これらのことから、両試験に対応できる参考書・テキストはほとんど見られません。
実施団体であるきんざいが、教材を発行していますので、そちらを使うのが一般的です。
通信講座ならば、自分で参考書を選ぶ必要がない
通信講座でFP2級を学習すると、教材のひとつとしてテキストがついていますので、自分で書店に足を運んで参考書を吟味する必要がありません。
過去問題を分析した結果から、出題される可能性が高いと思われる問題が厳選されていますので、効率の良い勉強ができます。
FP2級合格に向けて、このように参考書を選ぼう

FP2級の参考書についてご紹介しました。
合格を目標として自分に合った参考書を選ぶには、次の点を考慮すると良いでしょう。
参考書と問題集は同じ会社のものを選ぶのがお勧め
ひとつの参考書の中で、試験範囲が全て網羅されているものは存在しません。
参考書ごとで、少しずつ書かれている範囲が異なっています。
このため、参考書と問題集を同じ会社のもので揃える方が、わからないことがあったときに調べやすくなります。
異なる会社のものを選んでしまうと、問題集でわからないことがあっても、参考書に書かれていない事態が起こるかも知れません。
最新年度のものを選ぶ
FP2級の試験問題には、法令が大きく関係しています。
それぞれの試験実施月ごとで、法令基準日が定められており、それぞれの基準日に合わせた法令を把握していることが求められます。
1月と5月の試験であれば、前年10月1日が基準日となり、9月の試験では同年4月1日が基準日とされています。
この時点で、既に施行されているものが基準なのです。
最新年度に対応している参考書でないと、旧法令に基づいた問題となっており、試験対策ができなくなってしまうため、購入する際には十分注意しましょう。
1級受検を考えている人はきんざいの参考書が役立つ
きんざいにおける実技試験のひとつ「中小事業主資産相談業務」は、出題の範囲や傾向がFP1級試験の学科試験と似ているという特徴があります。
「中小事業主資産相談業務」では、法人税申告書や企業年金など、ほかの実技試験では出題されない範囲がありますが、この範囲が1級試験の範囲の一部に該当するためです。
中小事業の実技試験に対応できる参考書は、きんざいが発行している参考書に限られています。
2級に合格した後すぐに1級の受検を考えている方には、この参考書が役立ちます。
きんざいの実技試験に対応した通信教育なら、資格のキャリカレ
資格のキャリカレの教材は、FP 2級における6科目の学科試験に加えて、日本FP協会・きんざい双方が実施する実技試験に対応しています。
きんざいの実技試験に対応している通信教育はキャリカレのみであり、得意科目を選んで試験に挑むことができます。
・ FP(ファイナンシャルプランナー)とはどんな資格?取得すると就ける職業は?
・ FP1級の合格率と難易度は?難関と言われる理由と合わせてご紹介
読みやすいテキスト(参考書)には落とし穴あり?!
参考書を選ぶとき、読みやすさを重視する人も多いのではないでしょうか。
読みやすいと勉強しやすいと思いがちですが、スラスラ読める分内容が薄いこともあるので注意が必要です。
ページが少ない、イラストが多いなど読みやすさの要素がいくつかありますが、内容を吟味しないと試験に必要な知識を十分に身につけられない可能性があります。
知識が足りないと感じるタイミングは、問題集や過去問を解いたときです。
思うように正解できなかったときに、使用していたテキストでは不十分だったと感じるでしょう。
問題演習に取り組む段階は試験勉強の終盤であり、新しいテキストを購入したり、持っているテキストを読み直したりする時間は少ないです。
そうならないためには、読みやすさよりも情報量に注目して参考書を選びましょう。
ページ数が多い参考書は網羅性が高い傾向があり、試験に必要な知識が多く記載されています。
ボリュームがある分、慣れるまで使いこなすのは大変ですが、隅々まで理解できれば、合格の可能性が大きくアップするでしょう。
当然、中身をしっかり理解するまでに読みやすいテキストよりも時間がかかるので、学習時間をしっかり確保することが大切です。
FP2級に合格するには、どのような問題集が必要なの?
FP2級試験の合格を目指すには、問題集の活用が欠かせません。
どのような問題集を選ぶべきなのでしょうか。
過去問問題集で傾向をつかむ
FP2級の試験対策として、過去問を解くのが重要な位置づけとなっています。
過去問を解くことで、試験全体の傾向をつかみ、頻出される用語や問題が分かるようになります。
さらに、実技試験では、過去問の数字や設定を少し変えて、繰り返し出題されることも多いため、この対策として過去問の演習は必須です。
過去問は、全問正解するまで解き続けましょう。
これにより、得た知識が脳に定着します。
それぞれの科目で、出題される傾向が特に強く見られるテーマは、次のとおりです。
| 科目 | テーマ |
|---|---|
| ライフプランニングと資金計画 | FPと関連法規、公的年金 |
| リスク管理 | 生命保険商品、生命保険と税金 |
| 金融資産運用 | 金融商品と税金 |
| タックスプランニング | 所得の計算、所得控除 |
| 不動産 | 賃貸契約、建築基準法、不動産の譲渡 |
| 相続・事業承継 | 贈与税の計算 |
もちろん、これらのテーマ以外にも、幅広く勉強することが大事です。
ただ、タックスプランニングに含まれる「個人と法人の住民税・事業税」は、過去数年間ほぼ出題されていません。
出ないと言い切ることはできませんが、出題頻度が低いものは勉強の割合を減らし、ほかの科目で確実に得点できるようにした方が、効率を上げられます。
まとめ
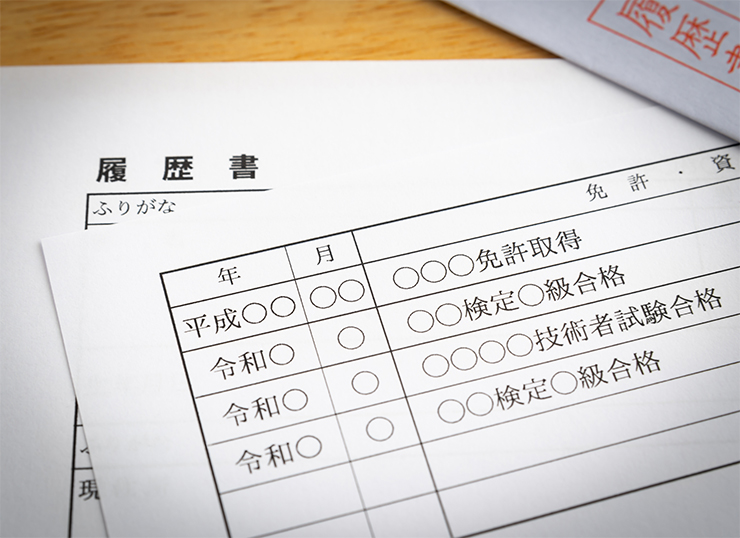
FP2級の参考書・テキスト選びをする時は、自分が選択した実技試験が学べるものになっているかを、事前に確認して選びましょう。
受検しない実技試験のものを購入してしまうと、試験対策が出来なくなってしまいますので、注意が必要です。
また、実技試験の内容もちろんですが、最新の対策がしっかりされているのかどうかも気にして選びましょう。
そのあたりが不安な方は、資格のキャリカレの通信講座を選択するとよいでしょう。
最新の試験対策がされたわかりやすい参考書・テキストはもちろん、理解を深めるために映像講義を見て学ぶこともできます。
スマホから講義を見られるので、学習場所を自由に選べ、生活スタイルに合わせて学べるのも大きなメリットです。
わからない点があれば、専任講師に直接質問でき、疑問をすぐに解決することもできます。
是非この機会に、資格のキャリカレで、FP2級合格を目指してみてはいかがでしょうか。
不合格なら全額返金保証つき!