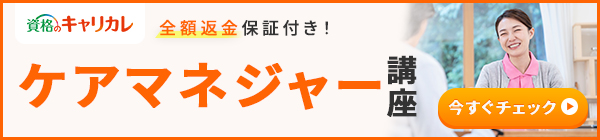ケアマネジャー(介護支援専門員)は国家資格?
受験資格や取得方法・将来性など詳しく解説

こんにちは、資格のキャリカレ編集部です。
30~50代に差し掛かり、これから先で再就職や転職に役立つ資格を取得したいと考えている方は多いのではないでしょうか。超高齢社会の日本で求められているのが、介護に携わる人材です。
そこで検討したいのが、ケアマネジャー(介護支援専門員)。ケアマネジャーはケアマネ、ケアマネージャーとも呼ばれる都道府県が認定する公的資格です。取得すると介護のエキスパートとして活躍できます。すでに介護福祉士として実務経験がある方は、次のステップとしてケアマネジャーがおすすめです。
本記事では、ケアマネジャーが国家資格化する可能性や概要、将来性などについて解説しています。試験日程やおすすめの学習方法についても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
※全額返金保証には条件があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
ケアマネジャーは国家資格?

意外に思われるかもしれませんが、ケアマネジャーは国家資格ではありません。各都道府県によって認定される公的資格で、正式名称を「介護支援専門員」といいます。介護に関する資格の中で国家資格と認められているのは、2024(令和6年)10月時点で介護福祉士のみです。
ケアマネジャーには、介護が必要な人が適切な介護サービスを受けられるようにサポートするという大切な役割があります。一人ひとりに合わせたケアプランを作成し、関係各署との連携を図るのが主な仕事です。個人情報の取り扱い(プライバシーポリシー)にも気を付けないといけません。また、介護保険の給付管理や介護全般の相談対応、要介護認定の申請代行・訪問調査といった業務も担っています。
ケアマネ試験を受験するには、介護福祉士や社会福祉士などの国家資格に基づく実務経験が5年以上かつ900日以上必要です。長い年月がかかるのは、介護という仕事がそれだけ専門的であり、豊富な経験や知識が求められるためといえるでしょう。すでに介護福祉士として活躍している方が次のステップとして目指したい職がケアマネジャーです。
ケアマネジャーが国家資格化する可能性は?
現在は公的資格と位置づけられるケアマネジャー資格ですが、一般社団法人日本介護支援専門員協会が国家資格化に向けた準備を進めています。2003年に政府が閣議決定した答弁書の添付資料に「国家資格一覧」があり、その中に「介護支援専門員」と記載されていたためです。
2024年現在まで、ケアマネジャーが国家資格として正式に認められた事実はありません。
しかし、介護支援専門員が国家資格と並ぶ専門性の高い資格であると政府が見解を示しましたので、今後国家資格化される可能性は十分に考えられるでしょう。
ちなみに、文部科学省によると、国家資格とは「国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格」と定義されています。つまり、ケアマネジャーを国家資格化するには、ケアマネ業務に関する法律を整備しないといけません。また、国家資格は「業務独占資格」「名称独占資格」「設置義務資格」「技能検定」の4種類あり、ケアマネジャーがどれに該当するのか、なぜそういえるのかの証明も必要です。
ケアマネジャーの資格は廃止される?
ケアマネジャーが国家資格化されるかもしれない動きがある一方で、「ケアマネジャーの資格が廃止される」といったうわさもあるようです。これからケアマネジャーになろうと考えている方にとっては、不安に感じてしまいますよね。
うわさの原因としては、科目免除制度の廃止や受験資格の厳格化が挙げられるでしょう。以前は国家資格保持者は一部科目の免除が認められていましたが、2015年に科目免除制度が廃止されてからは、全員が同じ試験科目を受けることになりました。
また、従来は介護の実務経験のみで受験資格を得られていたのが、2018年以降は実務経験だけで受験資格を満たすことはできない状況です。これらの影響で2015年と2018年の受験者数と合格者数が前年までと比べて激減したため、「ケアマネジャーの資格が廃止される」といううわさにつながったと考えられます。
しかし、実際にはケアマネジャー試験は毎年実施されていますし、そもそも介護業界にとってはなくてはいけない存在です。今後も必要とされる資格ですので、安心してください。
ケアマネジャーは国家資格ではないものの将来性がある理由

記事内で何度もお伝えしているように、ケアマネジャーは国家資格ではありません。にも関わらず、将来性がある資格として人気です。「高齢化社会が進んでいるため」「AIにはできない仕事内容のため」「介護に関する専門知識や高いスキルを持っているため」の3つの視点から、理由を見ていきましょう。
高齢化社会が進んでいるため
日本では、以前から少子高齢化が大きな問題となっています。急激に高齢化が進んだ結果、2007年には65歳以上の人口の割合が全人口の21%を占める超高齢社会へと突入しました。厚生労働省の発表によると、2070年には総人口が9,000万人を下回り、そのうち高齢化率は39%(約3,510万人)と推測されています。
また、同じく厚労省により、団塊の世代の人びと全員が75歳となる2025年には75歳以上の人口が全人口の約18%、2040年には65歳以上の人口が全人口の約35%に達するとの予測が発表されました。
少子高齢化によって高齢者が増加し続けると考えると、介護を必要とする人、つまりケアマネジャーによる支援を受けるべき人も増えることが予想されます。ケアマネジャーの資格を持っておくと、今後あらゆるシーンで活躍できるでしょう。
AIにはできない仕事内容のため
AIの台頭が著しい今、「ケアマネジャーの仕事をAIに取られてしまうのでは?」という声もよく聞かれます。ケアマネジャーの主な業務を見てみましょう。
・利用者へのヒアリングおよびケアプランの作成
・要介護認定などの申込手続きや支援
・病院・クリニックなどの医療機関や介護施設との連携
このうち、ケアプランの作成や要介護認定の申込といった事務系の作業・手続きは、確かにAIにもできるでしょう。しかし、一人ひとりに本当に適切な介護サービスを届けるには、直接利用者と向き合って相手の気持ちを理解し、細やかな気づかいができないといけません。
AIを活用するとしても、最終的には人の手で中身を確認する必要があります。
どんなにAI技術が進歩しようとも、人の「心」を正しく理解することはできません。逆にいえば、血の通った人間であるケアマネジャーだからこそ、利用者やご家族の気持ちに寄り添った思いやりのある支援ができるのです。
介護に関する専門知識や高いスキルを持っているため
ケアマネジャーは専門性が高く、介護全般に関する知識やスキルを身に付けています。初任の頃から頼りにされる存在といえるでしょう。ケアマネジャーを目指すには介護福祉士や社会福祉士などの国家資格を取得した上で実務経験を積んでいることが要件となりますので、受験のハードルがそもそも高いです。
また、ケアマネジャーは、介護保険にも精通しています。超高齢社会の今、介護保険は誰にとっても他人事ではありません。介護保険の知識があるケアマネジャーのニーズは、今後も高まっていくでしょう。
目の前の利用者と向き合うことで手一杯な医療や介護の現場では、介護保険に詳しい人材は貴重で重要な存在です。高度な知識やスキルを持つケアマネジャーがいれば、医療従事者や介護関係者から信頼を得やすいといったメリットもあります。
ケアマネジャーの試験内容
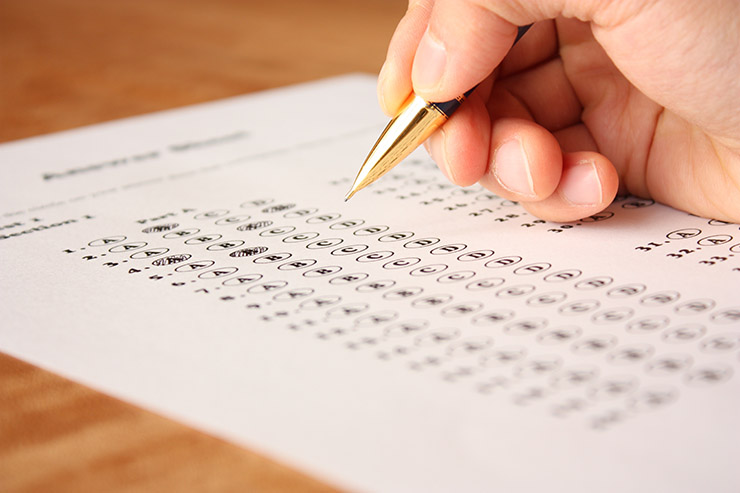
ケアマネジャー試験は、正式には介護支援専門員実務研修受講試験といいます。試験の内容について、詳しく見ていきましょう。
問題形式は、5つの選択肢の中から正しい答えを複数選んで回答する五肢複択式です。試験は勤務先もしくは住居地の都道府県で年に1回実施され、多くの都道府県でマークシート回答方式を採用しています。
試験時間は120分です。ただし、障がいなどの理由で配慮が必要な受験者の試験時間については、別途定められています。問題数は、全部で60問です。単純計算で1問あたり2分で解かないといけませんので、本番では時間配分に気を付けましょう。出題分野と問題数を表にまとめました。
| 出題分野 | 出題内容 | 問題数 |
|---|---|---|
| 介護支援分野 | 介護保険制度の基礎知識、要介護認定等の基礎知識、居宅・施設サービス計画の基礎知識等 | 25問 |
| 保健医療福祉サービス分野 | 保健医療サービスの知識等 | 20問 |
| 福祉サービスの知識等 | 15問 | |
| 合計 | 60問 | |
分野ごとの正答率70%程度が合格ラインといわれていますが、難易度に応じて毎年調整されているようです。ひとまず、各分野で70%以上の正答率を目指しましょう。
ケアマネジャーの資格取得方法と基本的な流れ

ケアマネジャーになるには試験に合格するのが大前提ですが、合格した後もやるべきことがあります。資格の取得方法とケアマネジャーになるまでの基本的な流れについて、詳しく見ていきましょう。
1.ケアマネジャーの資格試験に合格する
まずはケアマネジャー試験を受験し、合格しないといけません。試験は、毎年1回、例年10月に実施されます。受験する都道府県によってバラつきはありますが、4月から5月頃にかけて受験要項の配布時期や申込受付期間の詳細が公表されるのが一般的です。
5月から7月頃には、受験の申込手続きが始まります。書類を揃える期間も考慮して、早めに準備に取りかかりましょう。申込書類一式が無事にすべて受理されれば、試験日の約1ヶ月前に受験票が送付されてきます。受験票に記載されている内容や会場に間違いがないか、必ず確認してください。
試験本番は10月で、時間は午前10時から12時までの120分間です。合格発表は11月下旬から12月上旬にかけて行われ、郵送または各都道府県のサイトで通知されます。
2.介護支援専門員実務研修を受講する
ケアマネジャー試験に合格したら、所定の研修機関で介護支援専門員実務研修を受講しましょう。厚生労働省が定めた87時間以上のカリキュラム講習および居宅介護支援事業所での原則3日間の実習の受講が、修了の要件です。
研修の実施方法は、都道府県によって異なります。東京都の場合は、Zoomで演習を行うオンライン研修コースか会場で演習を行う集合研修コースのどちらかに参加が必須です。受講料は44,600円(非課税)で、振込の確認が取れた後、テキストなど研修に必要な資料が送付されてきます。
研修で学ぶのは、ケアプランの作成やモニタリングの実施、要介護認定といった知識や医療業界の基礎知識などです。ケアマネジャーとして働くためのより実践的な知識・スキルを身に付けられるでしょう。
3.介護支援専門員資格登録簿に登録する
研修を無事に修了したら、介護支援専門員資格登録簿への登録申請をします。研修修了後から3ヶ月を経過すると登録できなくなってしまいますので、早めに対応しましょう。
ここでは、東京都を例に、登録申請の流れを紹介します。必要な書類は、専門員証に使用する顔写真・研修の修了証書・本人確認書類の3点です。顔写真は正面・無帽・無背景で、顔全体がはっきりと映っているカラー写真を用意してください。
本人確認書類については、3ヶ月以内に取得した住民票・運転免許証(裏表両面)・マイナンバーカード(表面のみ)のいずれかで対応できます。ただし、住所変更がある方は、変更後の住所が記載されている書類を用意しましょう。
手続きは、電子申請で実施します。手数料1,500円は、申請後1ヶ月から1ヶ月半後に郵送する払込取扱票にて振り込んでください。
4.介護支援専門員証の交付を受ける
ケアマネジャーとしての業務を行うには、介護支援専門員資格登録簿への登録とは別に介護支援専門員証の交付を受ける必要があります。これがないと、ケアマネジャー業務に従事できません。
介護支援専門員証が交付されるまでに要する期間は、申請後1ヶ月間ほどです。手元に届いたら、ケアマネジャーとして業務を開始できます。専門員証の有効期間は5年間ですので、満了日までに所定の研修を受けて更新手続きをしてください。
なお、ほとんどの都道府県で介護支援専門員資格登録簿への登録時に介護支援専門員証の交付申請も行えます。「申請を忘れていた」といったことがないように、特段の事情がない限りは同時に申請しておくのがおすすめです。
ケアマネジャーの受験資格とは?

ケアマネジャー試験の受験資格は2018年から厳格化され、「所定の国家資格における業務」「相談援助業務」のどちらかについて5年以上かつ900日以上の実務経験がある者のみとなりました。
受験資格が厳格化された背景には、ケアマネジャーの質をさらに高めるためといった目的があります。それぞれの受験資格について、詳しく見ていきましょう。
所定の国家資格業務を有する場合
ケアマネジャー試験の受験資格を得られる国家資格は、以下の21種類です。
| 医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 保健師 | 助産師 |
| 看護師 | 准看護師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 社会福祉士 |
| 介護福祉士 | 視能訓練士 | 義肢装具士 | 歯科衛生士 | 言語聴覚士 |
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整体師 | 栄養士(管理栄養士含む) |
| 精神保健福祉士 |
これらの国家資格を保有しつつ、それぞれの資格に基づく業務で働き、通算5年以上かつ900日以上の実務経験がある方が対象です。実務経験に雇用形態は問われず、非正規雇用であっても要件を満たしていれば、受験資格を得られます。
ただし、国家資格を取得する前の介護業務、国家資格を保有していても経理や営業といった対人援助以外の業務に携わっていた場合は、実務経験に含まれません。また、育休や産休などの休業期間は年数・日数としてカウントされないことにも、注意が必要です。
相談援助業務の経験がある場合
各種施設の職員として働き、通算5年以上かつ900日以上の相談援助業務経験がある方も、ケアマネジャー試験の受験資格を得られます。具体的には、以下の業務です。
| 職種 | 業務内容 |
|---|---|
| 生活相談員 | 介護老人福祉施設や特定施設入居者生活介護において、要介護等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事。 |
| 支援相談員 | 介護老人保健施設において、要介護等の日常生活の自立に関する相談支援業務に従事。 |
| 相談支援専門員 | 障がい者総合支援法第5条第16項および児童福祉法第6条の2第6項に規定する事業の従事者として従事。 |
| 主任相談支援員 | 生活困窮者自立支援法第2条第2項に規定する事業の従事者として従事。 |
実務経験の年数・日数は、試験前日までの分をカウントできます。その場合は、受験申込時に実務経験見込証明書を添付して手続きを行ってください。
【2025年】ケアマネジャーに関連する国家資格介護福祉士の試験日程

2025年度のケアマネジャー試験については2024年10月現在、詳しい情報がまだ発表されていません。ここでは、ケアマネジャーに関連する国家資格・介護福祉士の試験日程について解説します。
| 試験名 | 介護福祉士国家試験 |
|---|---|
| 試験日程 | 2025年1月26日(日) |
| 試験科目 | ①人間の尊厳と自立/②人間関係とコミュニケーション/③社会の理解/⑨介護の基本/⑩コミュニケーション技術/⑪生活支援技術/⑫介護過程/④こころとからだのしくみ/⑤発達と老化の理解/⑥認知症の理解/⑦障害の理解/⑧医療的ケア/⑬総合問題 |
| 手数料 | 18,380円 |
| 合格発表 | 2025年3月24日(月)14時 |
介護福祉士は、介護の実務経験が3年以上あれば受験資格を得られます。介護福祉士の資格はケアマネジャー試験の受験要件ですので、介護業界でステップアップしていきたい方におすすめです。
介護福祉士国家試験の「受験の手引き」は、例年7月上旬頃から取り寄せできます。公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの公式ホームページで必要事項を入力し、送信してください。
ケアマネジャーや介護福祉士の学習はキャリカレがおすすめ

合格までのハードルが高いケアマネジャーの資格取得。自分だけで学習するのは難しい面もあるでしょう。介護のエキスパートともいえるケアマネジャーや介護福祉士の資格取得を効率的に目指すなら、キャリカレの通信講座がおすすめです。
・一発合格を目指せる
・不合格でも受講料を全額返金
・合格すれば2講座目が無料
一つずつ、詳しく解説します。
一発合格を目指せる
キャリカレの通信講座は、4ヶ月で合格を目指す短期集中型のカリキュラム編成です。最初の3ヶ月は試験に必要な知識の習得に専念し、残りの1ヶ月で徹底的に試験対策を行います。
テキストは、わかりやすさを重視したオリジナルの教材を使用。試験に出るところだけがギュッと凝縮されていて、効率的に学習できますよ。直近4年分の過去問題や本番と同形式の問題集など、試験対策用の教材が揃っているのも、嬉しいポイントです。
資格や試験について知り尽くした講師が講座を監修していますので、一発合格も夢ではありません。「資格を取りたいけれど、独学で勉強するのは不安」という方は、ぜひキャリカレの通信講座をチェックしてみてください。
不合格でも受講料を全額返金
通信講座を考えるとき、「不合格だったらお金が無駄になってしまう」と心配な方も多いのではないでしょうか。キャリカレには、試験に不合格だった場合に受講料を全額返金するサービスがあります。
受講料が無駄にならず、難関資格でもトライしやすいでしょう。全額返金保証サービスを受ける条件は、次の通りです。
・支払いの遅延がないこと
・サポート期間内にすべての添削問題を修了していること
・添削問題の平均得点率が70%以上であること
・事前に受験票のコピーをキャリカレ宛に送付できる方
「ケアマネジャー合格指導講座」「介護福祉士合格指導講座」は、どちらも全額返金保証の対象です。安心して取り組んでくださいね。
※全額返金には条件があります。詳しくはこちらをご覧ください。
合格すれば2講座目が無料
キャリカレには、対象の試験に合格すると2講座目を無料で受講できるサービスもあります。条件は、以下の通りです。
・キャリカレで2講座目無料サービス付きの講座を受講し、対象となる資格・検定試験に合格した方
・支払いの遅延がないこと
・受講開始日から3年以内に合格証明を提出できる方(当日消印有効)
・受講開始日から3年以内に2講座目の受講申込をする方(当日消印有効)
・体験談の提出に協力できる方
ケアマネジャー合格指導講座」「介護福祉士合格指導講座」は2講座目無料サービスの対象ですので、介護業界でスキルアップをしたい方にピッタリですよ。なお、2講座目無料サービスとして受講した講座については、全額返金保証サービス・返品・交換はできません。
※2講座目無料サービスには条件があります。詳しくはこちらをご覧ください。
ケアマネジャー国家資格化についてよくある質問

ここでは、ケアマネジャーの国家資格化についてよくある質問をまとめました。ケアマネジャーが国家資格化されない理由や介護福祉士資格との関係、ケアマネジャーが国家資格化された場合の賃金・待遇について解説します。
ケアマネジャーが国家資格にならない理由は?
ケアマネジャーは、業務独占資格や名称独占資格といった法的資格ではないため、国家資格とはいえません。
そもそも、何をもって国家資格と呼ぶのでしょうか。文部科学省によると、「国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格」と定義されています。介護福祉士が「社会福祉士及び介護福祉士法」という法律に基づいて業務が規定されているように、ケアマネジャーを国家資格化するには、ケアマネジャーに関する法律を整備しないといけません。
また、国家資格には「業務独占資格」「名称独占資格」「設置義務資格」「技能検定」の4種類あり、いずれかに分類されることも国家資格化の要件です。ケアマネジャーの法整備をし、国家資格のどの分類にあたるのか、また、なぜそこに分類されるのかを証明できれば、国家資格化への道が開けるかもしれません。
ケアマネジャーよりも国家資格の介護福祉士の方が上?
介護福祉士が国家資格であるのに対し、ケアマネジャーは公的資格です。国か都道府県レベルかで見たときに、国家資格である介護福祉士のほうが上なのではと感じる方もいるでしょう。
しかし、ケアマネジャーは、介護福祉士の資格を取得していないと受験資格を得られません。介護福祉士として実務経験を積んだ方が次に目指すのがケアマネジャーと位置づけられています。
どちらも介護業界で必要とされている職業ですし、誰でも取得できるような簡単な資格ではありません。また、業務内容や仕事上で発揮される専門性もそれぞれ異なります。「どちらが上で、どちらが下」といった上下関係に囚われるのではなく、介護業界でどう活躍したいのかという視点を持つことが大切です。
ケアマネジャーが国家資格になったら賃金や待遇は上がる?
もしケアマネジャーの国家資格化が実現すれば、賃金や待遇が改善されるという期待の声もあるようです。しかし、基本的に現状とほぼ変わらないと考えられています。
その理由は、国家資格化したところでケアマネジャーの業務そのものに変化が生じるわけではないためです。過去の事例を挙げると、柔道整復師が公的資格の立場から国家資格化されましたが、国家資格化されても業務内容に大きな変化は見られませんでした。また、企業側の視点でいえば、ケアマネジャーが国家資格化されたとしても業務内容がそれほど変わらないのなら、賃金を上げる理由がないでしょう。
とはいえ、介護業界の動きによっては、ケアマネジャーの賃金や待遇に影響が出る可能性は十分に考えられます。今後の動向に注目しておきましょう。
ケアマネジャーと介護福祉士のダブルライセンスをキャリカレで目指そう

ケアマネジャーは、都道府県が認定する公的資格です。介護福祉士を含む特定の国家資格を保有して実務経験を積んでいないと受験資格を得られないことから、介護福祉士が次のステップに進む資格として位置づけられています。
ケアマネジャーを目指すなら、介護福祉士とのダブルライセンスがおすすめです。キャリカレでは両方の講座に対応しており、短期集中型カリキュラムで一発合格を狙えますよ。
全額返金保証や2講座目無料(※)など、嬉しいサービスが充実しているのも、キャリカレの強みです。介護業界でのキャリアアップを考えている方は、キャリカレでダブルライセンスを目指しましょう。
※全額返金・2講座目無料には条件があります。詳しくは条件をご覧ください。
この記事の監修者
資格のキャリカレ編集部
150以上の通信教育資格講座を展開し、資格取得・実用スキルの習得はもちろん、キャリアサポートまで行う資格のキャリカレ編集部が運営するコラムです。
ケアマネジャーは介護や支援を必要とする方のサポートやマネジメントなどを行う仕事で、介護現場に欠かせない資格です。試験の詳細や対策、資格の魅力など、ケアマネジャーの最新情報をお伝えしています。