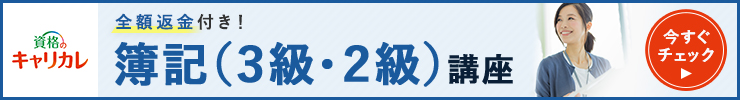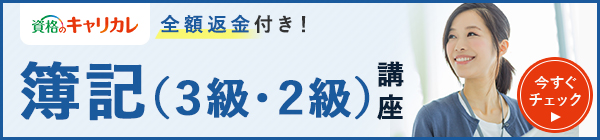精算表とは?書式と書き方を解説

精算表とは?書式や記入方法ってどうするの?といった、疑問にわかりやすく解説。精算表は、財務諸表を会計年度末に正しく作成するために用いるツールです。ここでは、精算表について詳しく知りたい人に向けて、概要や書式、記入方法について紹介します。
目次
精算表とは?

精算表はミスをなくすためのチェックシート
精算表は、財務諸表のうち貸借対照表と損益計算書のミスをなくす目的で作成するチェックシートです。
一般的に、企業は月末に仕訳や帳簿への転記ミスを洗い出す目的で試算表を作成します。
一方、決算期には試算表に網羅されていないデータを反映させる決算整理仕訳をしなければなりません。
決算は、下記のような流れで実施します。
- 1. 「残高試算表(決算整理前残高試算表)」の作成
↓ - 2. 「決算整理仕訳(修正記入)」
↓ - 3. 「損益計算書」および「貸借対照表」の作成
上記の4つの手続きを1つにまとめた表が精算表です。
表の見出しは、下記のようになります。
詳細は後述するため、イメージだけつかんでください。現金の記入例を記載していますが、0の部分は実際には何も書きません。
精算表
| 勘定科目 | 試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 現金 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
財務諸表にミスがあると企業の信用度が失墜するおそれがあるため、精算表を賢く活用してミスを防ぎましょう。
ここからは、各手続きの概要を解説します。
決算整理前残高試算表とは
決算整理仕訳の前に作成する残高試算表を決算整理前残高試算表といいます。
作成方法は、通常の残高試算表とまったく同じです。
残高試算表の借方と貸方を試算表欄の借方と貸方に転記しましょう。
試算表には、「合計試算表・残高試算表・合計残高試算表」という3種類がありますが、精算表では残高試算表を使う点がポイントです。
決算整理前残高試算表とは
企業の経営成績や、財政状況を正しく把握するために行う決算期特有の仕訳です。
決算整理仕訳は、精算表の修正記入欄に記入します。
主な決算整理仕訳には、消耗品の整理や減価償却費の計上、貸倒引当金の計上、売上原価の算出などがあります。
損益計算書とは
企業の経営成績を表す書類です。
仕訳で使う勘定科目は「資産」「負債」「純資産」「費用」「収益」という5つのグループに分類され、損益計算書には「費用」と「収益」を記載します。
借方と貸方は、下記のような関係になります。
簿記では借方と貸方が必ず等しくなる点に留意しましょう。
損益計算書
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 費用 | 収益 |
| 利益(収益―費用) |
貸借対照表とは
企業の財政状況を表す書類です。
「資産」と「負債」「純資産」の勘定科目を記載します。借方と貸方は下記のような関係になります。
貸借対照表
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 資産 | 負債 |
| 純資産(資産-負債) |
簿記資格取得を検討中の方に
簿記通信講座の資料お申し込みはこちら
精算表の書式
8桁精算表が使われるケースが一般的
精算表には、複数の書式があります。
しかし、前述した4つの手続きを網羅した8桁精算表が使われるケースが一般的です。
それぞれの手続きに貸方と借方があるため、1つの表にまとめると8桁になる仕組みとなっています。
決算整理後残高試算表を加えた10桁精算表や決算整理仕訳を省いた6桁精算表を使う場合もあります。
精算表にある貸借対照表および損益計算書の欄には、決算整理前残高試算表と決算整理仕訳をあわせた結果を記入しましょう。
例えば、決算整理前残高試算表に売掛金500円が計上されていて、決算時に売掛金の仕訳漏れ50円が新たに発覚した場合、残高試算表の借方と決算整理仕訳の借方を合計した550円が正しい数字です。
そのため、貸借対照表には550円を記入します。
漏れていた売掛金の仕訳例は下記の通りです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 売掛金 50 | 売上 50 |
精算表への記入例は、下記のようになります。
精算表
| 勘定科目 | 試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 現金 | 500 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 |
精算表の勘定科目
精算表に記入する勘定科目の並べ方は、試算表とほぼ同じです。
現金や当座預金などの「資産」をはじめに記入して、その下に「負債」「純資産」「収益」「費用」を記入する流れです。
一方、下記のような決算整理仕訳で使用する「費用」と「収益」の勘定科目は最後にまとめて記入します。
- 経過勘定科目(費用や収益の繰り延べや見越しで使う勘定科目)
- 貸倒引当金繰入(費用)
最後に当期純利益(純損失)を算出して記入します。
試算表と修正記入、損益計算書、貸借対照表の借方合計と貸方合計は必ず等しくなるため、一致しなかった場合は原因をつきとめましょう。
精算表の記入方法

ここからは、精算表の具体的な記入方法について解説します。
精算表の作成手順とルール
精算表の作成手順は、下記の通りです。
- 1. 通常通りに残高試算表を作成して精算表の試算表欄に転記
↓ - 2. 決算整理仕訳をして修正記入欄に記入し、試算表と修正記入を合算して損益計算書か貸借対照表の該当欄に記入
↓ - 3. 当期純利益(純損失)を算出
試算表と修正記入の合算結果は下記のルールに従って該当欄に記入します。
- 資 産:プラスなら貸借対照表の借方、マイナスなら貸方
- 負 債:プラスなら貸借対照表の貸方、マイナスなら借方
- 総資産:プラスなら貸借対照表の貸方、マイナスなら借方
- 収 益:プラスなら損益計算書の貸方、マイナスなら借方
- 費 用:プラスなら損益計算書の借方、マイナスなら貸方
例えば、プラスの「資産」となる現金は貸借対照表の借方に記入しますが、マイナスの「資産」を表す減価償却累計額は貸借対照表の貸方に記入しなければなりません。
売掛金や受取手形の貸し倒れに備える貸倒引当金もマイナスの「資産」にあたるため、貸借対照表の貸方に記入しましょう。
その勘定科目が「どのグループに該当するか」「プラスなのかマイナスなのか」を考えれば、どの欄に記入すべきなのかがわかります。
記入の具体例を紹介します。
実際の現金が帳簿より50円多い現金過不足が期内中に判明した場合の仕訳は、下記の通りです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 現金 50 | 現金過不足 50 |
決算整理仕訳は、下記のようになります。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 現金過不足 50 | 雑益 50 |
決算整理前の現金残高が500円だった場合、貸借対照表の借方に500を記入します。
現金過不足は試算表の貸方50と修正記入の借方50が打ち消しあうため、何も記入しません。
雑益は「収益」にあたるため、損益計算書の貸方に50を記入します。
精算表
| 勘定科目 | 試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 現金 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 現金過不足 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑役 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
ここからは、以下の決算整理仕訳について解説します。
- 経過勘定科目の決算整理
- 減価償却の決算整理
- 消耗品の決算整理
- 貸倒引当金の設定
- 売上原価の算出
- 当期純利益(純損失)の算出
経過勘定科目の決算整理
簿記では、「費用」と「収益」について当期に発生した部分と翌期分をきちんと分けて計上しなければなりません。
例えば、会計年度1~12月の事業者が11月に現金800円を年利率3%で貸し付けて、利息は1年後の返済時に受け取る契約をしたケースで考えます。
11月と12月分の利息は当期分の「収益」ですが、まだ受け取っていません。
現金を貸し付けたときの仕訳は、下記の通りです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 貸付金 800 | 現金 800 |
当期の受取利息は、800円×3%×2ヶ月÷12ヶ月=4円です。
決算整理仕訳は、下記のようになります。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 未収利息 4 | 受取利息 4 |
「資産」に該当する貸付金800円は、貸借対照表の借方に記入し、当期分の「収益」にあたる受取利息4円は試算表の残高と合算して損益計算書の貸方に記入しましょう。
未収利息4円は「資産」となり、貸借対照表の借方に記入します。
精算表
| 勘定科目 | 試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 貸付金 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 受取利息 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 未収利息 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
経過勘定科目のうち、前払費用と未収収益は「資産」、前受収益と未払費用は「負債」です。
減価償却の決算整理
建物や10万円以上の備品など減価償却の対象になる固定資産を保有している場合は、ルールに従って減価償却費を計上できます。
算出方法は複数ありますが、簿記入門編では、定額法を使用します。
定額法は、固定資産の価値が毎年同額ずつ減るとする考え方です。
定額法の減価償却費は、取得価額を耐用年数で割って求めます。
例えば、取得価額が1,800円で耐用年数が30年の建物を保有している場合、当期の減価償却費は1,800円÷30年=60円です。仕訳は下記のようになります。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 減価償却費 60 | 減価償却累計額 60 |
「費用」にあたる減価償却費は、修正記入と損益計算書の借方、マイナスの「資産」にあたる減価償却累計額は貸借対照表の貸方に記入します。
建物は金額が変わらないため、試算表と貸借対照表の借方に同じ数字を記入しましょう。
期内中に固定資産を取得した場合は月割計算で減価償却費を求めます。
例えば、会計年度1~12月の事業者がこの建物を前期の7月に取得した場合、使用期間は6ヶ月です。
減価償却費=60×6ヶ月÷12ヶ月=30
仕訳は下記の通りです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 減価償却費 30 | 減価償却累計額 30 |
前期までの減価償却累計額は当期分に引き継がれます。
なお、残存価額の概念は2007年の税制改正で廃止されました。
精算表
| 勘定科目 | 試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 建物 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 |
| 減価償却累計額 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
消耗品の決算整理
取得価額10万円未満か耐用年数1年未満の固定資産は、消耗品に該当します。
消耗品の仕訳方法は、2通りあります。
1つ目は購入時に消耗品を「資産」として計上する方法、2つ目は購入時に「費用」として計上する方法です。
どちらの方法でも、当期中に使った分だけを当期の消耗品費として計上しなければなりません。
残った消耗品は「資産」です。
例えば、購入時に下記のような仕訳をしたとします。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 消耗品費 100 | 現金 100 |
100円のうち80円分を使用した場合、決算整理仕訳は下記の通りです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 消耗品 20 | 消耗品費 20 |
この場合の精算表は下記のようになります。
精算表
| 勘定科目 | 試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 消耗品費 | 100 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
貸倒引当金の設定(差額補充法)
売掛金と受取手形に貸倒引当金を設定します。
例えば、売掛金と受取手形の合計が600円だった場合で2%の貸倒引当金を設定する場合なら、貸倒引当金の金額は600円×2%=12円です。
残高試算表に貸倒引当金の残高5円がある場合は、差額の7円を修正記入欄に計上して、貸借対照表の貸方に12円を記入します。
仕訳は、以下の通りです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 貸倒引当金繰入 7 | 貸倒引当金 7 |
貸倒引当金はマイナスの「資産」、貸倒引当金繰入は「費用」にあたります。
精算表
| 勘定科目 | 試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 貸倒引当金 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
売上原価の算出
売上原価とは、当期の売上にかかった仕入原価です。
売上原価は、下記の式で求めます。
売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高-期末商品棚卸高
例えば、期首商品棚卸高(繰越商品)が100円、当期の仕入が900円、期末商品棚卸高が50円だった場合の売上原価は、100円+900円-50円=950円です。
精算表で売上原価を計算する方法は複数ありますが、一般的に仕入の訂正記入欄で計算します。
仕入に期首繰越商品分100円を加算して、期末の繰越商品分を減らします。
仕訳は、下記の通りです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 仕入 100 | 繰越商品 100 |
| 繰越商品 50 | 仕入 50 |
繰越商品の修正記入欄には借方に50、貸方に100を記入し、仕入欄には借方に100、貸方に50を転記してから、それぞれの勘定科目で差額を算出します。
「資産」にあたる繰越商品の差額50は貸借対照表の借方、「費用」にあたる仕入の差額(売上原価)は損益計算書の借方に記入します。
精算表
| 勘定科目 | 試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 繰越商品 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 仕入 | 900 | 0 | 100 | 50 | 950 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益(純損失)の算出
当期純利益とは、損益計算書の貸方合計と借方合計の差額です。
プラスだった場合は損益計算書の借方、マイナスだった場合は貸方に数字を記入しましょう。
マイナスだった場合の勘定科目は当期純損失になります。
当期純利益は当期に増えた「純資産」を表すものでもあるため、プラスの場合は貸借対照表の貸方、マイナスの場合は借方に同じ数字を記入します。
精算表
| 勘定科目 | 試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 当期純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
損益計算書と貸借対照表の作成
精算表の結果を損益計算書と貸借対照表に転記しましょう。
損益計算書では仕入が売上原価、売上が売上高という名称に変わる点がポイントです。
貸借対照表では、繰越商品を商品として記入します。
簿記資格取得を検討中の方に
簿記通信講座の資料お申し込みはこちら
まとめ

精算表は、正しい損益計算書と貸借対照表を書くうえで欠かせないチェックシートですが、作成には簿記の幅広い知識が欠かせません。
難しそう…とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、簿記はルールがわかると意外と難しくないのでご安心ください。
そして、これから簿記資格の取得を目指す方におすすめしたいのが、資格のキャリカレの簿記資格講座(3級・2級)です。
はじめての人が悩んでしまうところや簿記試験に出るところをわかりやすく教えてくれるので、スラスラ学べます。
まだ簿記資格をお持ちでない方、これから資格取得を目指したいとお考えの方は、資格のキャリカレで資格取得を目指してみてはいかがでしょう。
この記事の監修者
資格のキャリカレ編集部
150以上の通信教育資格講座を展開し、資格取得・実用スキルの習得はもちろん、キャリアサポートまで行う資格のキャリカレ編集部が運営するコラムです。簿記は一度取得すれば、ビジネスにも家計にも役立つ資格です。簿記検定の詳細や試験対策をはじめ、仕分け・試算表の作成方法など、簿記の魅力や最新情報をお伝えしています。