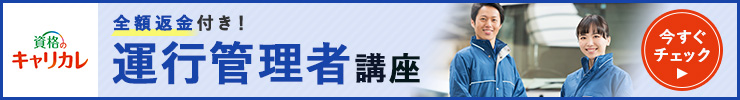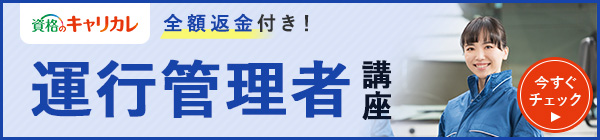運行管理者試験の合格率や難易度、勉強方法を詳しく解説

こんにちは、資格のキャリカレ編集部です。
運行管理者試験は、貨物または旅客の運行管理者資格証を取得するために必要な国家試験です。運送会社に勤務している人の中には、この資格証の取得を会社から命じられることもあるでしょう。なぜなら、営業所の保有車両ごとに有資格者の配置が法律で定められているからです。ここでは、運行管理者試験の合格率や試験概要、合格するための勉強法などについて解説していきます。
目次
-
- 始めやすい受講料
- 初心者でも最短4ケ月で資格取得可能
- わかりやすさにこだわった教材セット
- 万が一不合格でも全額返金
※全額返金には条件があります。詳しくはこちらをご覧ください。 - 合格した場合は2講座目が無料
※2講座目無料サービスには条件があります。詳しくはこちらをご覧ください。
運行管理者とは

運行管理者とは、運行管理者試験に合格した人の中から、貨物・旅客輸送の安全を管理する目的で運送会社に選任された人のことを言います。
運送業は交通ルールを守って安全に輸送することが大切であり、安全運行における指導監督の役割を担っているのが運行管理者です。
具体的な仕事内容は、ドライバーの勤務時間が記載された乗務割作成や対面での点呼、過労運転の防止、運行ルート指示など多岐にわたります。
運行管理者になる方法は、運行管理者試験に合格するか、一定の基準を満たした実務経験を積んでいるかの2種類です。
運行管理者の仕事内容

運行管理者の主な仕事は、事業用自動車が安全に運行できるよう、さまざまな場面で管理・手続きを行うことです。
具体的には、乗務員が適切に仮眠などを取ることができるよう、休憩するための施設を管理したり、正しい勤務時間範囲で乗務割を作成したりします。
また、乗務員の点呼・アルコール検知のほか、乗務状況の確認や記録を行うことも運行管理者の重要な業務です。
運行管理者になるためには

運行管理者には、試験に合格して資格を取得するか、基準年数以上の実務経験を積むか、いずれかの方法でなることができます。
詳しく見ていきましょう。
国家試験に合格する
国家試験に合格して運行管理者資格者証を取得する方法は、運営管理者として働くための近道です。
しかし、運行管理者の国家試験を受けるには、1年以上の実務経験か「基礎講習」の受講実績が必要となります。
基礎講習を受けたうえで国家試験にも合格すれば、どの運送事業でも運行管理者として働くことが可能です。
一定の条件を満たすことでもなれる
事業用自動車の運行管理に関わる実務を5年以上経験した人は、試験に合格していなくても運行管理者になれます。
運行管理者資格取得を目指すなら
無料パンフ請求はこちら
ただし、この5年の間に自動車事故対策機構などが実施する一般講習を5回以上受講しておくことも条件に含まれており、5回のうちの1回は「基礎講習」を受講していなければなりません。
運行管理者試験の受験資格
運行管理者試験には受験資格があり、受験するには以下の2つの条件のうちいずれかを満たす必要があります。
(1)運行管理に関して1年以上の実務経験
自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行管理に関し、1年以上の実務の経験を有する方。
(2)基礎講習修了、または修了予定
国土交通大臣が認定する講習実施機関において、試験の種類に応じた基礎講習を修了(または修了予定)した方。
出典:CBT試験新規受験申請|受験概要|公益財団法人 運行管理者試験センター
基礎講習を修了すると、運行管理者の補助者として働くことができるようになります。
試験に合格して運行管理者資格者証を得た人は、事業者ならびに一般の人たちの安全性を高め、法律やコンプライアンスを守る重要な責任を負うことを忘れてはなりません。
試験を受けるだけではなく、実務経験や基礎講習の修了を受験資格としている理由についても今一度確認しておきましょう。
運行管理者試験の試験概要
運行管理者試験を受けるときには、試験日程や会場を確認して申し込みを行う必要があります。
申し込み方法や受験手数料などについても、ここで確認しておきましょう。
特に試験日程は2021年度から変更点があるので注意が必要です。
試験日程
運行管理者試験は、令和元年3月の試験が新型コロナウイルスの影響で中止された以外、令和2年度までは毎年度8月と3月の年2回実施されてきました。
しかし、2021年度からパソコンを使って回答を行う「CBT試験」に全面移行されて以来、8月~9月と12月~翌年1月の期日内ならいつでも受験できるようになったので、日程に注意が必要です。
次回令和4年度第1回運行管理者試験は、以下の通りです。
試験日 :令和4年8月6日(土)~9月4日(日)
申請期日:令和4年6月13日(月)~7月13日(水)
なお、申請はインターネット申請のみとなっており、書面での申請はできません。
専用サイトから受験確認書のメールが送信されるので見逃さないように気をつけましょう。
試験を終えたら、約1ヶ月後に合格発表です。
受験番号は、試験センターのホームページに掲載されます。
受験手数料等
運行管理者試験の受験手数料は、非課税で6,000円です。
希望者のみですが、試験結果レポート手数料は140円かかります。
新規受験申請の場合、システム利用料として660円、再受験の場合、システム利用料+事務手数料として860円が別途かかるので注意しましょう。
支払い方法はコンビニ決済やクレジット決済、ペイジー決済が利用できます。
運行管理者試験の合格率はどのくらい?
運行管理者試験は「貨物」「旅客」の2種類に分けられています。
これから試験を受けようとしている人は、受験者数や合格率が気になるのではないでしょうか。
運行管理者試験合格率は、年度や試験日によってかなり変動するのが特徴です。
しっかりと内容について確認しておきましょう。
・運行管理者試験(貨物)の合格率
貨物の運行管理者試験は、令和元年(2020年)3月に予定されていた試験が新型コロナウイルスの影響で中止されましたが、年2回実施されています。
過去13回の試験において、受験者数は少ないときで約2万7,000人、多いときは3万9,000人を超えています。
7年間で30万人以上が受験しており、1回ごとの平均は約3万人です。
合格率は、試験日ごとに変動します。
平成28年~令和4年度までの7年間で最も高かったのが令和2年度第2回の43.9%、最も低かったのが、平成28年度第2回の20.5%です。
合格率の推移を見ていくと、平成24年度第1回までが合格率40%以上に対して、同年度第2回が24.3%、翌年平成25年度第1回が19.3%と急激な低下が見られます。
ただし、平成24年度第2回にかぎっては、大幅な難易度上昇が認められ、合格基準が引き下げられました。
それ以降も、合格率は試験日ごとに変動していますが、平均して全体の3割ほどです。
| 年度 | 受援者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 第1回 | 28,804人 | 11,051人 | 38.4% |
| 令和3年度 第2回 | 27,982人 | 9,028人 | 32.3% |
| 令和3年度 第1回 | 34,164人 | 10,164人 | 29.8% |
| 令和2年度 第2回 | 32,575人 | 14,295人 | 43.9% |
| 令和2年度 第1回 | 39,630人 | 12,166人 | 30.7% |
| 令和元年度 第2回 | 中止 | ||
| 令和元年度 第1回 | 36,530人 | 11,584人 | 31.7% |
| 平成30年度 第2回 | 29,709人 | 9,743人 | 32.8% |
| 平成30年度 第1回 | 35,619人 | 10,220人 | 28.7% |
| 平成29年度 第2回 | 29,063人 | 9,605人 | 33.0% |
| 平成29年度 第1回 | 37,774人 | 13,238人 | 35.0% |
| 平成28年度 第2回 | 29,621人 | 6,069人 | 20.5% |
| 平成28年度 第1回 | 36,028人 | 10,868人 | 30.2% |
運行管理者資格取得を目指すなら
無料パンフ請求はこちら
・運行管理者試験(旅客)の合格率
旅客の運行管理者試験においても、令和元年(2020年)3月の試験は中止されています。
令和4年度まで、過去13回の試験を見ていくと、令和4年度第1回が最少人数である5,403人、平成29年度第1回には最多人数となって1万人を超えました。
受験者数は、概ね7,000~9,000人ほどで推移しており、受験者数は9万人以上、試験ごとの平均受験者数は約8,000人です。
旅客の運行管理者試験の合格率も、試験日ごとに変動があります。
最も合格率の低かった開催年は令和2年度第1回の31.2%、最も高かったのが令和2年度第2回の47.4%でした。
貨物の試験に比べると合格率の上がり下がりは少なく、平成28年~令和4年度の平均合格率は30%前後です。
貨物、旅客ともに合格率は3割ほどと覚えておけば間違いないでしょう。
| 年度 | 受援者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 第1回 | 5,403人 | 2,167人 | 40.1% |
| 令和3年度 第2回 | 5,787人 | 1,999人 | 34.5% |
| 令和3年度 第1回 | 6,740人 | 2,196人 | 32.6% |
| 令和2年度 第2回 | 7,610人 | 3,604人 | 47.4% |
| 令和2年度 第1回 | 9,714人 | 3,026人 | 31.2% |
| 令和元年度 第2回 | 中止 | ||
| 令和元年度 第1回 | 8,263人 | 2,624人 | 31.8% |
| 平成30年度 第2回 | 7,605人 | 2,868人 | 37.7% |
| 平成30年度 第1回 | 8,998人 | 2,856人 | 31.7% |
| 平成29年度 第2回 | 8,588人 | 2,928人 | 34.1% |
| 平成29年度 第1回 | 10,462人 | 3,694人 | 35.5% |
| 平成28年度 第2回 | 8,028人 | 2,085人 | 36.0% |
| 平成28年度 第1回 | 8,169人 | 2,876人 | 34.1% |
運行管理者試験の難易度は?

運行管理者試験の難易度は、年々上がっている傾向です。
ここでは、合格率に見る難易度の推移や、難易度が上がることになったきっかけについて解説していきます。
CBT試験対策についてもしっかり確認しておきましょう。
(1)一夜漬けの勉強では無理?合格率に見る難易度の推移
運行管理者試験の受験をするには、運行管理に関する実務経験が1年以上あることが求められます。
そのため、受験者の中には仕事をしながら勉強を続け、試験に臨む人が少なくありません。
試験の合格率は、上述した通り貨物・旅客ともに3割程度です。
実務経験者は、当然ながら基礎的な知識や経験を身につけています。
そうした人たちが受験する中で、合格率約3割というのは、なかなか厳しい数字だと見ておいたほうが無難でしょう。
また、運行管理者試験は、たび重なるツアーバス事故などの影響で「年々難易度が上がっている」といわれています。
実際に、貨物の運行管理者試験における合格率は、平成23年度は第1回が46.8%、第2回が47.8%と5割近い人が合格していました。
しかし、令和2年度第1回の合格率は30.7%と合格率が16%以上も下がっていることが分かります。
このような背景があるため、長い実務経験があったとしても、一夜漬けのような勉強のやり方で試験に臨むことは避けたほうがよいでしょう。
(2)難易度が上昇した理由は?
運行管理者試験の難易度が上昇した1つのきっかけとして、平成28年1月に起きた軽井沢スキーバス転落事故が挙げられます。
長野県軽井沢町の国道で、乗員を乗せた大型観光バスが道路脇に転落した事故です。
乗員・乗客41人のうち、15人が亡くなる大事故でした。
当時、業界では慢性的な運転手不足が叫ばれており、「事故を起こしたバス運転手の労働環境や運転技量に問題がなかったか」などが厳しく問われました。
この事故を受けて、国土交通省は有識者委員会を立ち上げ、バス事業者や旅行業者に乗客の安全・安心を最優先するように指導を実施。
具体的には、安全確保違反の業者への罰則が引き上げられ、経験の浅い運転手に対する実技訓練や貸切バスへのドライブレコーダー設置が義務化されました。
乗員・乗客の命を守るためにも、適切な運行管理やルール遵守がこれまで以上に求められています。
その中で、運行管理者の果たす役割は非常に大きいといえるでしょう。
(3)CBTの導入でパソコンに慣れておくことが必要
運行管理者試験では、令和3年度第1回より、パソコンで試験に解答するCBT試験に全面移行されています。
パソコンを使い慣れている人でも、CBT試験を理解していないと、普段は解けたはずの問題が途端に難しく感じてしまうこともあるでしょう。
そのため、精神面での動揺が試験に悪い影響を与えないように、CBT試験のパンフレットを事前にしっかりと読んでおくことも重要です。
また、パソコンをあまり使わない人は、試験までに少しでも操作に慣れておく必要があります。
合格ラインは何点?
運行管理者試験について、貨物と旅客両方の出題分野や設問数、合格点について確認していきましょう。
合格ラインを把握しておくと、設問全体の中から解答に自信のある問題を選ぶことができます。
(1)運行管理者試験(貨物)の試験科目と合格点
貨物の運行管理者試験における試験科目(出題分野)は、5種類(分野)です。
それぞれ設問数も毎年同じなので、確認していきましょう。
まず、設問数8と最も多い「(1)貨物自動車運送事業法関係」で、貨物に関する基本的な法律です。
次に、設問数4の「(2)道路運送車両法関係」と設問数5の「(3)道路交通法関係」、設問数6の「(4)労働基準法関係」と続きます。
最後は、設問数7の「(5)その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力」です。
これだけは、法律に直接関わることではないため、試験内容が多岐にわたります。
他の試験科目も同様ですが、過去問を参考にしっかりとした試験対策をしておきましょう。
(2)運行管理者試験(旅客)の試験科目と合格点
旅客の運行管理者試験における試験科目(出題分野)も、貨物と同様に5種類(分野)です。
実は、1つの科目以外貨物とまったく同じ試験科目になります。
唯一異なるのは、貨物が「(1)貨物自動車運送事業法関係」だったのが、旅客の場合には「(1)道路運送法関係」になるだけです。
設問数も同じく8問となります。
(3)運行管理者試験の合格点(貨物・旅客共通)
運行管理者試験の設問数は、全部で30問。
合格点(合格ライン)としては、総得点が60%以上です。
つまり、30問中18問以上正解すればよい計算になります。
注意しなければならないのは、法律について科目が4つありましたが、各科目で正解が1問以上なければ合格できません。
さらに、「(5)その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力」においては、2問以上の正解が求められます。
(4)どんな設問があるの?
○×問題の場合は、問題とともに○と×が画面に表示されるので、正答だと思う方をマウスでクリックしていきます。
解答し終えれば「次へ」をクリックし、次の問題に移っていきます。
本番で慌てないために、試験の方式を良く理解し心構えを持っておくことが大切です。
パターンを覚えてしまえば試験中に戸惑うこともなくなります。
事前の準備が重要になってくるでしょう。
ただ、そのパターンを覚えてしまえば試験中に戸惑うこともなくなります。
事前の準備が重要になってくるでしょう。
運行管理者の資格取得のメリット
運行管理者の資格を取得するメリットは主に3つあります。
資格保有者は必須の存在
運行管理者は営業所に一定の人数を配置しなければならないため、資格保有者は需要があることです。
ネットショッピングの普及から運送業はこれからも人手不足が見込まれ、運行管理者は安定して職に就けると予想できます。
昇進・昇給できる
昇進や昇給が見込めることです。
運行管理者は運送業の重要任務である安全運行の管理監督を担うため、管理職としてキャリアアップが図れます。
また、会社によっては資格手当を支給している場合もあり、昇給できます。
自分の裁量で仕事を決められる
自分の裁量で仕事を決められるためやりがいを持てることです。
乗務割の作成やドライバーへの指示など自ら判断する場面が多く、仕事に対して充足感を持てます。
運行管理者試験に合格するための勉強方法とは?
運行管理者試験の受験者には、働きながら試験勉強をしている人も多いのではないでしょうか。
少ない時間でできるだけ多くの成果を得るには、効率的な勉強法が欠かせません。
ここでは、3つの勉強方法について解説します。
(1)わかりやすいテキストを入手する
運行管理者試験では、法律関連の設問が多い傾向です。
しかし、本格的な法律の勉強を始めることはおすすめできません。
なぜなら、仕事を抱えた忙しい状況で法律の基礎から勉強するのは時間が足りないからです。
そこで、効率よく学べる教材が必要となります。
運行管理者試験の対策とされている参考書や問題集の中にも、「要点が絞りきれていないもの」「赤色などでポイントを押し出しすぎてかえって見にくくなっているもの」などがあります。
試験に出るところだけを重点的にカバーして、必要十分な解説をしている本を入手すべきです。
運行管理者試験の勉強法は、無駄なく分かりやすい教材をそろえることが第一歩となります。
(2)最新の過去問で出題形式を確認する
運行管理者試験の特徴として、過去の焼き増しのような問題が多い傾向です。
試験を作る側としても、試験範囲が限定されているため、前回までの試験からかけ離れた設問を作ることはできない一面があるといえるでしょう。
そうした傾向を踏まえると、過去問を解くのは必須の勉強法です。
ある程度の試験内容を頭に入れたら、どんどん過去問を解いていきましょう。
反復して問題を解いていくことで、試験の傾向にも慣れていきます。
ただし、法改正などで解答そのものが違ってしまったり、それまでの試験には出題されていなかった設問が足されたりすることもあるため、テキストは必ず最新版を選びましょう。
(3)CBT試験を理解する
令和3年度第1回から、運行管理者試験は「CBT試験」に全面移行されています。
CBT試験では、問題用紙やマークシートを使用しません。
設問を読むのも、解答するのもパソコン画面を見ながら操作します。
解答するときには、マウスを使って選択するだけのため、タイピングなどの必要はありません。
CBT試験は、受験の申請から受験確認書の受け取りまで、すべての手続きをインターネット経由で行うことが可能です。
試験当日は、運転免許証などの写真付きの身分証明書に加えて、メールで送信されてきた受験確認書を持参しましょう。
受験確認書は、スマートフォンで表示できるようになっていれば問題ありません。
運行管理者資格取得を目指すならどこがおすすめ?
運行管理者試験の合格を目指すなら、資格のキャリカレの「運行管理者(貨物・旅客)合格指導講座」がおすすめです。初心者でもわかりやすい教材や業界トップクラスの手厚いサポート体制で、より確実に合格を目指せる講座になっています。
ここでは、講座の特徴を5つ見ていきましょう。
始めやすい受講料
講座の受講費用は、WEB申込でハガキ申込価格から1万円割引になり、分割払いも可能なので無理なく始められます。
お得に学べるキャンペーンも随時開催されており、家計への負担を抑えて受講できるのが魅力的です。
※ハガキ申込価格とは、ハガキ・フリーダイヤル・FAX等、Webサイト(インターネット)以外からのお申し込みの際の、各種割引(受講生割引、紹介割引、WEB申込割引)等が適用されていない価格を指します。
初心者でも最短4ケ月で資格取得可能
講座は、初心者からでも最短4ケ月で学べるカリキュラムを組んでいます。
学習手順や試験対策などの学習法を丁寧に指導しているため、知識ゼロからでも安心して取り組めるのが特徴です。
わかりやすさにこだわった教材セット
テキストは試験に出るところが赤字で色付けされていたり、難しい用語もわかりやすく解説されているので、すらすら学べます。
もし難しい内容があっても、映像講義できちんと補足されているので、無理なく理解しながら学べます。
映像講義は、スマホやPCなどで視聴できるので、外出先でも学べます。
スキマ時間で効率よく学習できるので、忙しい方でも安心です。
万が一不合格でも全額返金
講座を受講したにも関わらず不合格になってしまった場合でも、受講料の全額返金を受けられます。
そもそもの受講料がお手頃なだけではなく、不合格でも保証を受けられるので受講して損はありません。初心者でも失敗を恐れずに勉強を始められるのが嬉しいポイントです。
※全額返金には条件があります。詳しくはこちらをご覧ください。
合格した場合は2講座目が無料
晴れて運行管理者試験に合格できた場合は、資格のキャリカレで2講座目を無料で受講できます。
キャリカレには運行管理者資格と相性の良いビジネス関連資格や趣味の資格などが豊富に揃っているため、気になる講座を続けて受講してみましょう。
※2講座目無料サービスには条件があります。詳しくはこちらをご覧ください。
講座の詳細は、下記のボタンから確認できます。受講を検討する際に、一度チェックしてみましょう。
まとめ

運転管理者試験(貨物・旅客)の合格率や試験概要、勉強法などを解説してきました。
受験資格として実務経験が要求されるため、働きながら試験勉強をする人も多いのではないでしょうか。
しかし、働きながらだと疲れてきった状態で勉強を進めるため、思い通りに進まないと苦戦することも多いようです。
そんな状態の中で、無駄なく効率的な勉強を進めるためには、試験に出るところが端的にわかりやすくまとめられた教材で学習することが大切です。
そこでおすすめなのが、資格のキャリカレが提供する運行管理者(貨物・旅客)合格指導講座です。
資格のキャリカレの運行管理者講座なら、ラクに勉強できる教材と万全な試験対策で仕事しながらでもムリなく合格が目指せます。
また、学習に関する質問が無料で出来ることはもちろん、万が一不合格なら受講料が全額返金されるので安心です。
これから試験に挑戦される方は、ぜひ資格のキャリカレのホームページを確認してみてください。
この記事の監修者
資格のキャリカレ編集部
150以上の通信教育資格講座を展開し、資格取得・実用スキルの習得はもちろん、キャリアサポートまで行う資格のキャリカレ編集部が運営するコラムです。運行管理者は大型トラックやバス、タクシーなどのドライバーの管理・指導する資格です。運行管理者試験の詳細や試験対策をはじめ、魅力や最新情報をお伝えしています。