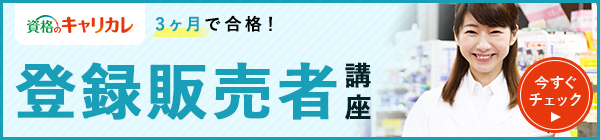登録販売者試験の難易度と合格率は?
都道府県別実績や他資格との比較まで紹介!

こんにちは、資格のキャリカレ編集部です。
登録販売者試験の難易度は?合格率は?登録販売者試験って難しいの?とお悩みの人はこちらをご覧ください。登録販売者試験の合格率を都道府県別にご紹介。受験者データや合格ラインなど、登録販売者試験についてわかりやすくご紹介します。
目次
-
- 始めやすい受講料
- 初心者でも最短3ケ月で取得可能
- とにかくわかりやすい教材セット
- 万が一不合格だった場合、受講料を全額返金
※全額返金には条件があります。詳しくはこちらをご覧ください。 - 合格した場合、2講座目を無料で受講できる
※2講座目無料サービスには条件があります。詳しくはこちらをご覧ください。
\累計受講数2万人突破!/
キャリカレの登録販売者講座を見る登録販売者の試験は難しい?難易度は?

まずは、登録販売者の試験の難易度について解説します。
登録販売者試験の難易度はどのくらい?
登録販売者資格試験について「難しそう」というイメージを持っている人は多いかもしれません。
平成26年(2014年度)までは、学歴や実務経験などの受験資格が必要だったため、専門の人が取得する資格と考えていた人もいるでしょう。
しかし、現在は受験資格の条件がなくなり、誰でも受験できます。
そして、出題範囲をきちんと押さえて学べば、合格は決して難しくないのです。
出題範囲を理解していれば決して難しくない
登録販売者試験に合格するためのコツは、出題範囲を理解し、その内容を重点的に勉強することです。
なぜなら、地域によって試験内容は違うものの、厚生労働省が作成した「試験問題の作成に関する手引き」に沿った内容が出題されるからです。
つまり、この内容を繰り返し学び、模擬問題を解けるようになれば、合格する可能性は高くなります。
独学の場合、勉強時間はどのくらい必要?
難易度の目安として、勉強時間がどのくらい必要かも気になる方が多いのではないでしょうか。
登録販売者の合格に必要な勉強時間の目安は、250~300時間前後です。
平日1日あたり2時間、休日1日あたり4時間勉強した場合は、3~4ケ月で必要な知識を身につけられるでしょう。
とはいえ、仕事や家事などで毎日勉強できないこともあるかと思います。
試験内容としては出題範囲を理解できれば難関ではないので、1日5分でもテキストを開き、継続して勉強すれば誰でも合格のチャンスがあります。
登録販売者試験の出題範囲と合格ライン

次に、登録販売者試験を合格するためにも、出題範囲と合格ラインを把握しておきましょう。
登録販売者試験の出題範囲
登録販売者試験のベースとなる、厚生労働省の「試験問題の作成に関する手引き」は一般に公開されています。
それによると、出題範囲の1項目目は「医薬品に共通する特性と基本的な知識」、2項目目は「人体の働きと医薬品」、3項目目は「主な医薬品とその作用」です。
そして、4項目目が「薬事関連法規・制度」、5項目目が「医薬品の適正使用・安全対策」となっています。
これらの内容は医薬品全般に関する基本的な知識です。
登録販売者が扱うのはドラッグストアなどで市販されている「一般医薬品」の第2類医薬品と第3類医薬品のみです。
安全上特に注意が必要な第1類医薬品は扱えません。
しかし、医薬品全般に関してお客様から問い合わせをうけることもあります。
その際に正しい回答ができるように、登録販売者として基本的な知識を網羅していることが必要です。
登録販売者試験の合格ライン
登録販売者試験に合格するには、まず、全問題の70%以上の正答が必要です。
問題数は1問1点で120問なので、84問以上の正答が求められます。
さらに、先述した5項目の出題分野すべてで35%以上、都道府県によっては40%以上の正答が必要です。
試験の難易度自体は年度によってほぼ変わりません。
全国平均の合格率は少しずつ下がっていますが、これは未経験者や勉強不足の受験者が増えたためだと推測できます。
2013年の受験者2万8527人に対して2019年の受験者数は6万5288人と、2倍以上になっているからです。
登録販売者試験の合格率

では、実際、登録販売者の試験を受けた方の合格率はどのくらいなのでしょうか?ここからは、登録販売者試験の合格率を解説していきます。
登録販売者試験の合格率の推移
登録販売者試験の全国平均の合格率は44.3% となっています。 2012~2022年の受験者数・合格者数・合格率推移は以下のとおりです。
| 試験実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 5万5606人 | 2万4707人 | 44.4% |
| 2021年度 | 6万1070人 | 3万82人 | 49.3% |
| 2020年度 | 5万2959人 | 2万1953人 | 41.5% |
| 2019年度 | 6万5288人 | 2万8328人 | 43.4% |
| 2018年度 | 6万5500人 | 2万7022人 | 41.3% |
| 2017年度 | 6万1126人 | 2万6606人 | 43.5% |
| 2016年度 | 5万3369人 | 2万3330人 | 43.7% |
| 2015年度 | 4万9864人 | 2万2901人 | 45.9% |
| 2014年度 | 3万1362人 | 1万3627人 | 43.5% |
| 2013年度 | 2万8527人 | 1万3381人 | 46.9% |
出典:厚生労働省|これまでの登録販売者試験実施状況等について
都道府県別合格率
2022年度の登録販売者試験の都道府県別合格率は以下のようになっています。
| 都道府県名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,005 | 1,043 | 52.0% |
| 青森県 | 672 | 328 | 48.8% |
| 岩手県 | 687 | 286 | 41.6% |
| 宮城県 | 1,491 | 736 | 49.4% |
| 秋田県 | 460 | 187 | 40.7% |
| 山形県 | 526 | 228 | 43.3% |
| 福島県 | 1,343 | 564 | 42.0% |
| 茨城県 | 1,316 | 636 | 48.3% |
| 栃木県 | 853 | 370 | 43.4% |
| 群馬県 | 1,808 | 1.033 | 57.1% |
| 埼玉県 | 2,579 | 1,034 | 40.1% |
| 千葉県 | 2,910 | 1,158 | 39.8% |
| 東京都 | 4,570 | 1,898 | 41.5% |
| 神奈川県 | 3,216 | 1,433 | 44.6% |
| 新潟県 | 920 | 464 | 50.4% |
| 富山県 | 613 | 250 | 40.8% |
| 石川県 | 734 | 297 | 40.5% |
| 福井県 | 444 | 136 | 30.6% |
| 山梨県 | 510 | 286 | 56.1% |
| 長野県 | 948 | 474 | 50.0% |
| 岐阜県 | 999 | 405 | 40.5% |
| 静岡県 | 1,652 | 761 | 46.1% |
| 愛知県 | 3,171 | 1,380 | 43.5% |
| 三重県 | 672 | 301 | 44.8% |
| 奈良県 | 601 | 287 | 47.8% |
| 鳥取県 | 220 | 82 | 37.3% |
| 島根県 | 373 | 126 | 33.8% |
| 岡山県 | 858 | 337 | 39.3% |
| 広島県 | 1,054 | 450 | 42.7% |
| 山口県 | 512 | 225 | 43.9% |
| 香川県 | 467 | 204 | 43.7% |
| 愛媛県 | 623 | 241 | 38.7% |
| 高知県 | 362 | 108 | 29.8% |
| 福岡県 | 2,426 | 1,415 | 58.3% |
| 佐賀県 | 1,328 | 787 | 59.3% |
| 長崎県 | 558 | 308 | 55.2% |
| 熊本県 | 780 | 423 | 54.2% |
| 大分県 | 571 | 332 | 58.1% |
| 宮崎県 | 433 | 231 | 53.3% |
| 鹿児島県 | 829 | 420 | 50.7% |
| 沖縄県 | 619 | 276 | 44.6% |
| 関西広域連合 | 7,893 | 2,767 | 35.1% |
| 年 度 計 | 55,606 | 24,707 | 44.4% |
登録販売者試験は都道府県ごとに実施されており、問題も都道府県によって異なることから、合格率にばらつきがでます。
合格率が高いのは北海道・東北、合格率が低いのは四国
登録販売者試験は各都道府県で実施され、試験内容が異なります。
試験日も違うため、複数の都道府県で受験することも可能です。
厚生労働省では難易度を全国で統一するために「試験問題の作成に関する手引き」を作成しています。
エリアごとの合格率ですが、従来は北海道・東北地方が合格率の上位にランクインすることが多いなど、特定の地域の合格率が高くなる傾向にありました。
たとえば北海道、東北地方における2015~2018年の合格率は50%を超えており、全国平均より5~10%程度高く、反対に四国エリアでは同期間の合格率が32.1%と平均より低いなど、地域ごとにばらつきがあったのは事実です。
ただ最近は、かつて合格率が高かった北海道・東北よりも中国地方のほうが高い合格率の年も出てくるなど、年によって若干の傾向はありながらも、大きな偏りは見られなくなりつつあります。
登録販売者試験と他資格の比較

ここからは、登録販売者と別の資格を比較しながら、難易度について深掘りしていきます。
医薬品関連での難易度の違い
医薬品に関わる有名な資格と言えば、国家資格「薬剤師」が挙げられます。
薬剤師はまず6年間大学の薬学部に通う必要があり、そこから国家試験を受験します。
国家試験自体の合格率は約80%と高いですが、大学の薬学部に入学することが、高いハードルとなります。
一方、登録販売者は、厚生労働省や文部科学省などの官庁・大臣・都道府県などが認定する資格で、国家資格ではありません。
そして、今では学歴や実務経験がなくても誰でも受験できる人気資格になっています。
受験資格がないだけでなく、合格率も40~50%と高めなので、比較的やさしい部類に入る試験です。
通信講座などの対策講座も充実していることもあり、医薬品に関わる資格の中では、登録販売者が取得しやすい資格と言えるでしょう。
登録販売者試験の過去問
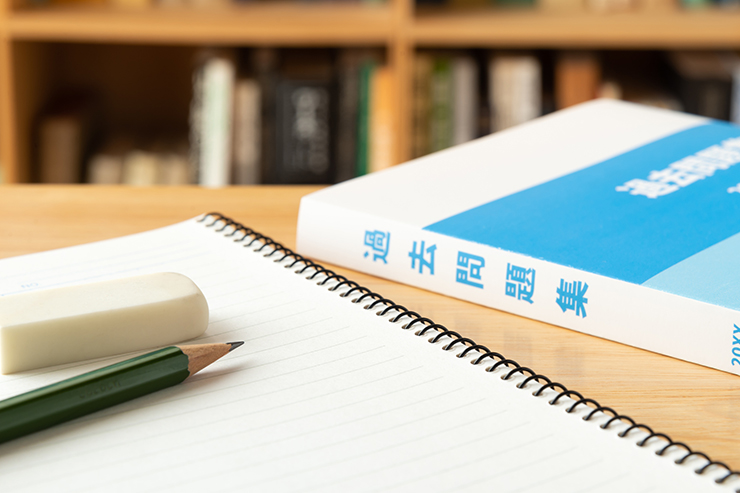
登録販売者試験合格に向けて勉強する際は、過去問を効果的に活用するのがポイントです。
過去問によって試験の傾向をつかみ、実践的な知識を身につけたり、時間配分の感覚がわかったりするので、試験準備の集大成として取り組みましょう。
登録販売者試験の過去問は、各都道府県のホームページなどにまとめられています。
以下の記事でも過去問を都道府県別にまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
【2023年最新】令和5年度登録販売者試験の概要
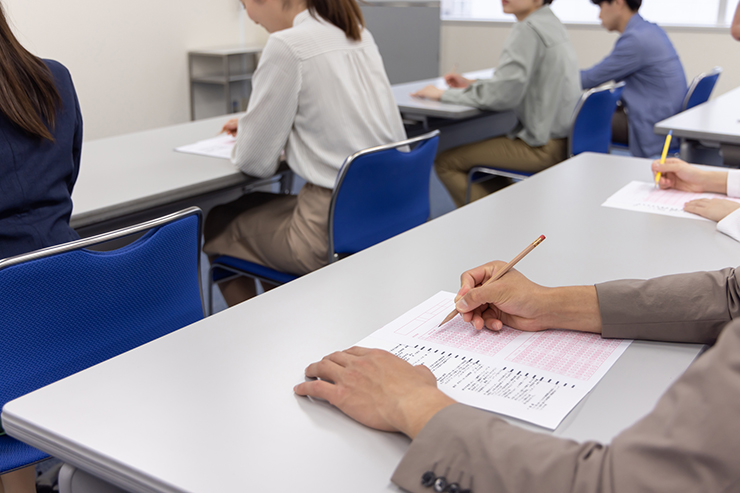
2023年度に実施される令和5年度登録販売者試験は、以下の内容で行われる予定です。
受験を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
なお、下記の表は東京都の試験概要です。
必ず自身が受験する地域の案内を確認しましょう。
| 試験日時 | 令和5年9月10日(日) 10:00~15:30(9:30までに着席) |
|---|---|
| 試験会場 |
|
| 受験受付期間 | 令和5年5月22日(月)〜6月2日(金) |
| 受験申請書類 |
|
| 受験手数料 | 13,600円 |
| 試験項目・問題数 |
|
| 出題範囲 | 厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月)」に準ずる |
| 合格発表日 | 令和5年10月20日(金) |
登録販売者試験の申し込み方法

登録販売者試験を受験するためには、受験申請が必要です。
都道府県ごとに受験者への案内を実施しているので、案内にしたがって書類の提出や手数料の納付を行いましょう。
まず、各都道府県で定められた受験願書、写真台帳、入力通知書などの必要書類を保健所などの指定された提出先に送付します。
手数料はこれまで受験願書に貼り付ける方法でしたが、令和5年度から電子納付ができるようになりました。
決済手数料はかかりますが、クレジットカードでの支払いが可能です。
また、受験手続きには期日が定められており、期日を過ぎていると申請を受け付けられないため、必ず期日内に申し込みしましょう。
登録販売者試験に合格するための勉強方法

登録販売者試験の出題範囲は、概ね厚生労働省が公開している医薬品・医療機器に関する「試験問題作成に関する手引き」の範囲内です。
この手引きには人体機能から医薬品の効能解説、副作用・薬害の歴史に至るまで、医薬品に関する知識・情報が網羅的に掲載されています。
この内容を全て暗記すれば登録販売者試験に合格できるかもしれませんが、実際に丸暗記は不可能と言わざるを得ません。
大切な勉強方法は、自分が受験する地域の過去問数年分をくり返し解くことと、試験合格のためのポイントを絞ったわかりやすい参考書・テキストを選んで勉強することです。
モチベーションを保たないと合格レベルの学力に至ることは難しいため、独学を検討している方は毎日の勉強時間と解く問題の分量を決めておくなどの工夫をしましょう。
登録販売者ができること

登録販売者は国家資格である薬剤師とは一線を画する資格です。
しかし、薬剤師が人材不足傾向にあるなかで、登録販売者がにわかに注目を浴び、資格受験者は増加しています。
登録販売者ができる業務にはどのようなものがあるのでしょうか。
詳しく見てみましょう。
一般用医薬品(第2類・第3類に限る)販売が可能
登録販売者は、比較的副作用リスクが低いとされる医薬品の販売を行えます。
具体的に販売可能なのは第2類・第3類に分類されている医薬品で、この範囲を超える医薬品を販売することはできません。
登録販売者になると、ドラッグストアやコンビニエンスストアなど、第2類・第3類の医薬品を販売している店舗などで、お客様に薬の飲み方や副作用等について説明することが可能です。
登録販売者試験に合格するならどこがおすすめ?

登録販売者資格の合格を目指すなら、資格のキャリカレの「登録販売者合格指導講座」がおすすめです。初心者にも取り組みやすいカリキュラムとわかりやすい教材、丁寧なサポートで、より確実に合格を目指せる講座になっています。
ここでは、講座の特徴を5つ見ていきましょう。
始めやすい受講料
講座の受講費用は、WEB申込でハガキ申込価格から1万円割引になり、分割払いも可能なので無理なく始められます。
お得に学べるキャンペーンも随時開催されており、家計への負担を抑えて受講できるのが魅力的です。
※ハガキ申込価格とは、ハガキ・フリーダイヤル・FAX等、Webサイト(インターネット)以外からのお申し込みの際の、各種割引(受講生割引、紹介割引、WEB申込割引)等が適用されていない価格を指します。
初心者でも最短3ケ月で取得可能
講座は、登録販売者試験に精通した講師が監修・指導しており、初心者からでも最短3ケ月で学べるカリキュラムを組んでいます。
学習手順や試験対策などの学習法がわかるため、初心者でも安心して取り組めるのが特徴です。
とにかくわかりやすい教材セット
テキストは試験に出るところが赤字で色付けされていたり、難しい用語もわかりやすく解説されているので、すらすら学べます。
もし難しい内容があっても、映像講義できちんと補足されているので、無理なく理解しながら学べます。
映像講義は、スマホやPCなどで視聴できるので、外出先でも学べます。
テキストだけでは理解できないときに心強い講義です。
万が一不合格だった場合、受講料を全額返金
講座を受講したにも関わらず不合格になってしまった場合でも、受講料の全額返金を受けられます。
そもそもの受講料がお手頃なだけではなく、不合格でも保証を受けられるので、初心者でも失敗を恐れずに勉強を始められるのが嬉しいポイントです。
※全額返金には条件があります。詳しくはこちらをご覧ください。
合格した場合、2講座目を無料で受講できる
晴れて登録販売者試験に合格できた場合は、資格のキャリカレで2講座目を無料で受講できます。
キャリカレには登録販売者資格と相性の良いビジネス関連資格や趣味の資格などが豊富に揃っているため、気になる講座を続けて受講してみましょう。
※2講座目無料サービスには条件があります。詳しくはこちらをご覧ください。
講座の詳細は、下記のボタンから確認できます。受講を検討する際に、一度チェックしてみましょう。
\累計受講数2万人突破!/
キャリカレの登録販売者講座を見るまとめ

登録販売者試験の難易度は、きちんと勉強すれば誰でも合格できるレベルです。
しかし、全体で70%以上、各出題範囲すべてで35%(40%)以上の正答をするには、ポイントを押さえた勉強が欠かせません。
過去に出題された問題を繰り返し解くのも効果的です。
登録販売者資格の取得を目指して自宅で学習をはじめるなら、わかりやすい教材や効率良く学べるカリキュラムがあり、しっかりとした学習サポートがある通信講座キャリカレの「登録販売者講座」がおすすめです。
忙しい社会人の方や、家事や育児をしている主婦の方などでも、空いた時間を使って自分のペースで学習できます。
是非この機会に登録販売者資格の取得を目指してみませんか?
\累計受講数2万人突破!/
おすすめの登録販売者講座はこちらこの記事の監修者
資格のキャリカレ編集部
150以上の通信教育資格講座を展開し、資格取得・実用スキルの習得はもちろん、キャリアサポートまで行う資格のキャリカレ編集部が運営するコラムです。登録販売者は薬剤師に次いで一般用医薬品(市販薬)を販売できる専門職です。登録販売者試験の詳細や試験対策をはじめ、魅力や最新情報をお伝えしています。