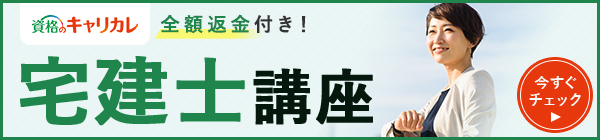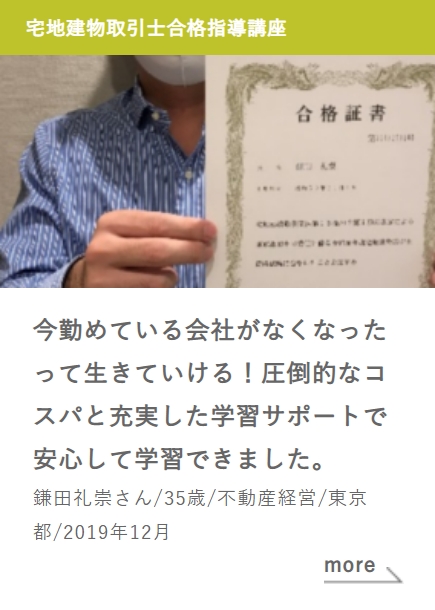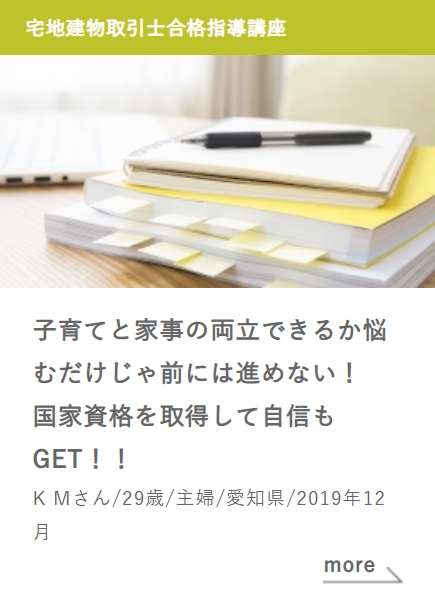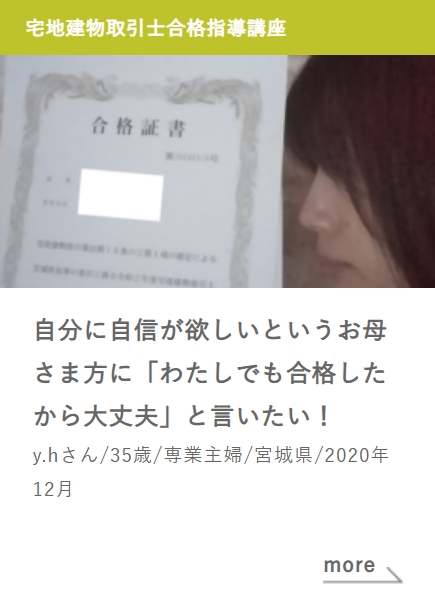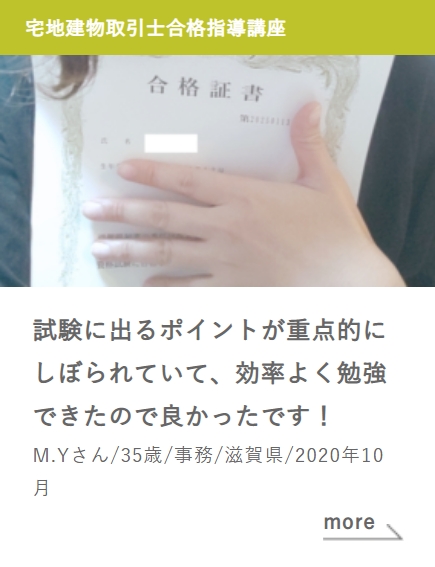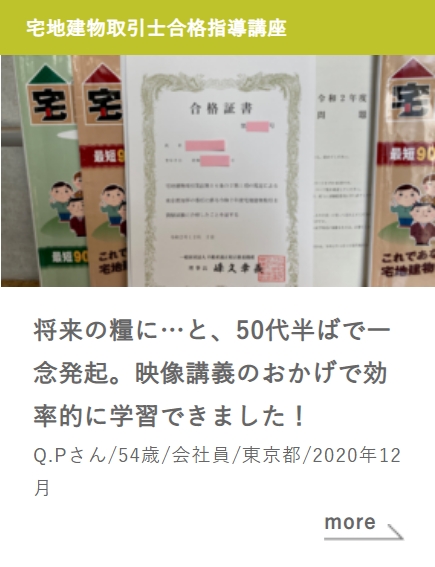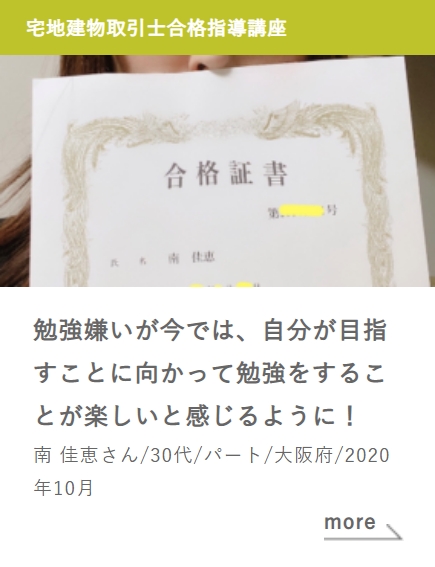2023年(令和5年)の宅建試験日と申し込み~合格までの日程

こんにちは、資格のキャリカレ編集部です。
令和5年度(2023年)宅建試験(宅地建物取引士資格試験)の試験日時、申込方法、受験料、合格発表をはじめ、受験資格、試験科目と問題数・配点、合格基準まで、ここでは、宅建試験に関する情報をわかりやすく解説します。
目次
宅建試験は年に何回実施されるの?
宅建試験の実施回数は年1回です。
例年10月の第3日曜日に全国の都道府県で実施され、合格発表は11月の最終水曜日または12月の第1水曜日となっています。
申し込みは例年7月からはじまりますので、忘れのないように注意しましょう。
宅建の平均受験回数は?
宅建試験に合格するまでの平均受験回数は約2回です。
ただし、40%以上の方が1回の受験で合格しており、あくまで平均回数が2回となります。
なお、2回目で合格した方が約30%、3回目で合格した方が約10%となっており、3回目までの試験で合格した方が、90%を占めています。
令和5年度(2023年)の宅建試験情報
令和5年度(2023年)の宅建試験は、まだ公式発表されていないため、下記の概要は例年通り実施された場合の内容です。
公式と相違がある場合もあるので、正式な情報を必ず確認してください。
試験日時
令和5年10月15日(日)13時~15時(2時間)
※試験当日は、注意事項の説明がありますので、12時30分までに着席。
※途中退出はできません。途中退出した場合は、棄権または不正受験とみなされます。
※試験日が変更になる可能性がありますので、必ず試験実施団体ホームページでご確認ください。
合格までのスケジュール
令和5年の宅建試験(宅地建物取引士資格試験)の、試験案内から合格発表までのスケジュールを紹介します。
| 試験案内の掲載・ 配布 |
令和5年7月1日~7月31日 |
|---|
| ▼ |
| 受験申込の受付 | 【インターネット】 令和5年7月1日(土)9時30分~7月15日(土)21:59まで 【郵送】 令和5年7月1日(土)9時30分~7月31日(月)まで |
|---|
| ▼ |
| 受験票発送日 | 未定 |
|---|
| ▼ |
| 試験日 | 令和5年10月15日(日) |
|---|
| ▼ |
| 合格発表 | 令和5年11月21日(火) |
|---|
受験資格
宅建試験(宅地建物取引士資格試験)に、受験資格はありません。
年齢・性別・国籍の制限もありませんので、どなたでも受験できます。
試験会場
宅建試験は、全国の都道府県で実施されます。
試験地は、原則として住民登録している都道府県が会場となり、試験会場は受験票に記載されています。
学生や単身赴任等の事情で、住民登録とは別のところに住んでいる場合、今住んでいる都道府県で受験することができます。
同じ都道府県内に複数会場ある場合は、先着順で指定することができます。
ただし、インターネットからの申込に限ります。
受験手数料
8,200円
※受験手数料は、消費税及び地方消費税は非課税です。
申込方法
「インターネット」または「郵送」で行います。
合格発表
令和5年11月21日(火)
午前9時30分からホームページで発表
試験形式
四肢択一式によるマークシート形式です。
※問題数:50問。試験時間:2時間。
※詳しくは試験実施団体である一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページでご確認ください。
試験科目と問題数・配点
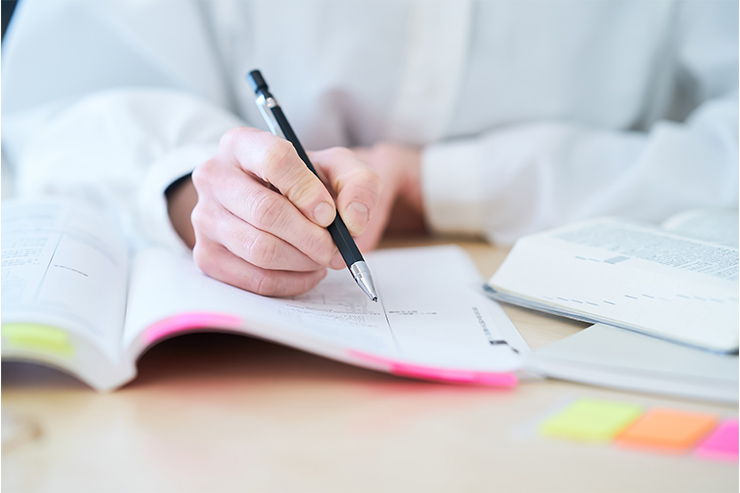
宅建試験の試験科目は、「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限」「税・その他」の4科目です。
科目別の問題数、配点は以下のようになっています。
| 科目 | 問題数 | 配点 |
|---|---|---|
| 宅建業法 | 20問 | 20点 |
| 権利関係 | 14問 | 14点 |
| 法令上の制限 | 8問 | 8点 |
| 税・その他 | 8問 | 8点 |
合格基準
宅建試験の合格基準(合格ライン)は、年度によって異なります。
年度によって変動はあるものの、35点前後が合格基準(合格ライン)の目安になっています。
確実に合格するなら、37点以上を目指しましょう。
なお、過去10年間の合格基準(合格ライン)は以下のようになっています。
| 年度 | 合格率 | 合格点 |
|---|---|---|
| 令和4年度 | 17.0% | 36点 |
| 令和3年度 (10月実施分) |
17.9% | 34点 |
| 令和2年度 (12月実施分) |
13.1% | 36点 |
| 令和2年度 (10月実施分) |
17.6% | 38点 |
| 令和元年 | 17.0% | 35点 |
| 平成30年 | 15.6% | 37点 |
| 平成29年 | 15.6% | 35点 |
| 平成28年 | 15.4% | 35点 |
| 平成27年 | 15.4% | 31点 |
| 平成26年 | 17.5% | 32点 |
| 平成25年 | 15.3% | 33点 |
宅建試験のおすすめの勉強法は?
宅建試験の勉強法には、独学で勉強する方法と通信講座で勉強する方法があります。
ここでは、宅建試験に合格するために、それぞれのメリットやデメリットを紹介していきます。
独学のメリット・デメリット
【メリット】費用が安い
まず一つ目は、テキストなどの勉強に必要な費用が安く収まるということです。
通信講座や通学に通うとなると、テキストだけではなく受講料が必要になるため、金銭的な負担が大きくなります。
しかし、独学で必要なのは、テキスト(参考書)や過去問題、模擬問題集(練習問題集)のみです。
書店などで、自分が学びやすそうなテキストや問題集を購入するだけで済むので、安く学ぶことができます。
【メリット】自由に学べる
2つ目は、ご自身のライフスタイルにあわせて自由に学べることが挙げられます。
独学は、時間と場所を選ばない学習スタイルです。
早朝や深夜でも学習できるので、日中働いている人でも、ご自身の都合に合わせて勉強時間を確保できます。
また、隙間時間でも学習可能なので、仕事の休憩時間や通勤時間、家事育児の合間でも、好きな時間に勉強できます。
【デメリット】モチベーション維持が難しい
独学のデメリットとしては、モチベーション維持の難しさが挙げられます。
独学の場合、勉強するかしないかは本人次第です。
そのため、もし予定通りに勉強できなかったとしても、その週にリカバリーするなど、やる気や計画性を持っていないと、継続するのは難しくなります。
わからないところが出てきても、誰も教えてくれないため、不明点は割り切ることも必要になります。
継続的な学習を続けられるように、努力することが大切になります。
【デメリット】最新情報が手に入りにくい
2つ目のデメリットには、最新情報・法改正情報の把握が難しいことが挙げられます。
宅建の試験内容は、毎年法改正に伴い変更されるので、最新の教材と問題集で学習を進めないと、間違った情報を覚えてしまう可能性があります。
また、わからない部分を調べようとインターネットなどで調べる際も、書かれている内容が、最新の情報ではないケースも多いため注意が必要です。
通信講座のメリット・デメリット
【メリット】自由に学べる
1つは、独学同様に自由に学べる点が挙げられます。
通信講座は独学と同じく、早朝や深夜、通勤中や家事の合間など、ご自身の好きな時間を使うことができます。
また、外出先でもスマホで映像講義を確認しながら勉強することもできるため、場所を選ばずしっかりと学習に取り組めます。
【メリット】講師に質問できる
2つ目は、わからないところは講師に質問できることです。
通信講座では、無料で講師に質問できるところがほとんどです。
そのため、わからないところをそのままにしなくてすむので、疑問を残さず学び進めることができます。
なお、実際に講師と対面するわけではなく、メールなどを使って質問するため、時間もかかりません。
通学では、講義終了後の限られた時間などでしか質問できない場合もあります。
また、人によっては、他の生徒の合間を縫って質問することが難しい場合もあります。
その点、通信講座では時間などを気にする必要がないので、ストレスなく質問できます。
【メリット】試験対策された教材が届く
3つ目は、過去の試験傾向から合格対策がなされた教材が届くことです。
宅建試験に関する知識がない方にとって、教材・参考書選びはとても大変です。
わかりやすそうでも内容が薄かったり、丁寧なようで重要なポイントが抜けていたりと、教材・参考書選びは難しいのです。
その点、通信講座では長年のノウハウをもとに、初心者にもわかりやすいことはもちろん、過去の傾向を踏まえた合格対策万全の教材を用意してくれます。
また、法改正されているので、安心して学習を進められます。
【デメリット】独学と比べると費用が必要
通信講座のデメリットは、独学と比べると費用が掛かることです。
独学がテキスト・参考書を購入しても1万円前後で収まるところが、通信講座だと3万円~6万円くらい必要になります。
ただし、通信講座の受講料は、通学・スクールよりもかなり安くなっている点ではかなりお得と言えます。
わからないところを講師に質問できること、試験対策された良い教材で勉強を進められることを考慮すると、通信講座を選択する価値は高いと言えます。
以上のメリットやデメリットを踏まえ、宅建士試験に短期間で合格したい方には、資格のキャリカレの「宅地建物取引士合格指導講座」がおすすめです。
ぜひ以下のリンクから詳細をチェックしてみてください。
法改正を反映した教材・過去問を入手することがポイント
宅建試験では4月1日時点で施行されている法令であれば、その年の試験に反映されます。
そのため、最新の法改正情報を入手することが合格への必須条件となります。
宅建試験は、通常35点以上を獲得できれば合格に近づくことができます。
残り1点・2点でこのラインを達成できなかった方がかなり多いのが現状です。
確実に1点を取りに行くためにも、最新の法改正情報が反映された教材を入手しましょう。
早めの対策を心掛ける
宅建試験の合格を目指すなら、何より早めの対策が必要です。
勉強開始が遅れてしまうと、スケジュールを立てるのが難しくなり、十分な対策ができないまま試験当日を迎えてしまうかもしれません。
勉強に使える時間を把握した上で、余裕を持って勉強に取り組めるように学習を早めに始めましょう。
宅建試験の勉強開始におすすめの時期

宅建試験の合格には、約200~300時間の勉強時間が必要になると言われています。
勉強時間を300時間とした場合、1日2時間で約5ヶ月の期間が必要です。
試験は毎年10月に実施されているので、遅くても5月頃から勉強を始めると良いでしょう。
仕事や家事などの都合で勉強時間が少なくなる場合は、さらに早めに始めると安心です。
まとめ

宅建試験は、受験資格がなく誰でも受験できることや、四肢択一のマークシート方式であることから受験者数も多く、人気の国家資格です。
受験者数が多いこともあり、合格率は約15%と低めの試験ですが、7割以上を正答できれば、合格が出来る試験です。
しっかりとした対策を行えば確実に合格を勝ち取ることができますので、頑張って対策に取り組みましょう。
そして、これから宅建士を目指すあなたにおすすめなのが、キャリカレの「宅地建物取引士合格指導講座」です。
キャリカレなら、わずか3カ月で学ぶカリキュラムで、宅建士になるために必要な学びだけを厳選しており、宅建士に必要な知識がしっかり身につきます。
また、試験を受けて万が一不合格だった場合は受講料を「全額返金」。
さらに、見事合格すれば「2講座目が無料で受講できる」サービスもあるので安心です。是非この機会に宅建士講座をはじめてみませんか?
※全額返金と2講座目無料サービスには条件があります。詳しくはそれぞれの条件をご覧ください。(・全額返金の条件 ・2講座目無料サービスの条件)
90日で宅建士を
一発合格するための講座
宅建士の資格を取りたい!だけど…
「何から手をつければいいかわからない…」
「仕事しながら合格できるかな…」
など、学習の不安や悩みはありませんか?
本講座なら、仕事をしながらでも90日で宅建士合格が目指せます。
- 2,000名以上を合格に導いた専門講師が監修
- スマホでカンタンに学べる映像講義
- 12ヶ月の長期サポート完備
など、短期間で一発合格ができる理由をお確かめください。
必要事項の入力は10秒で完了。
後はお手元に届くのを待つだけです。
ぜひ、無料資料で詳細をご覧ください。
簡単10秒でお申込み完了!
この記事の監修者
資格のキャリカレ編集部
150以上の通信教育資格講座を展開し、資格取得・実用スキルの習得はもちろん、キャリアサポートまで行う資格のキャリカレ編集部が運営するコラムです。宅地建物取引士は不動産業界への就職や転職などに役立つ資格です。宅地建物取引士試験の詳細や試験対策をはじめ、魅力や最新情報をお伝えしています。